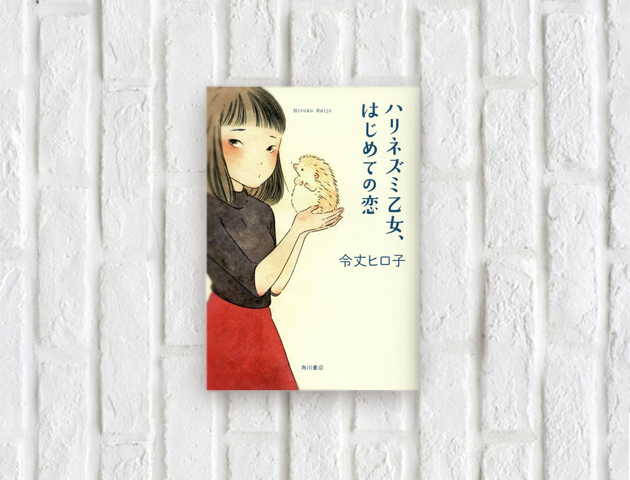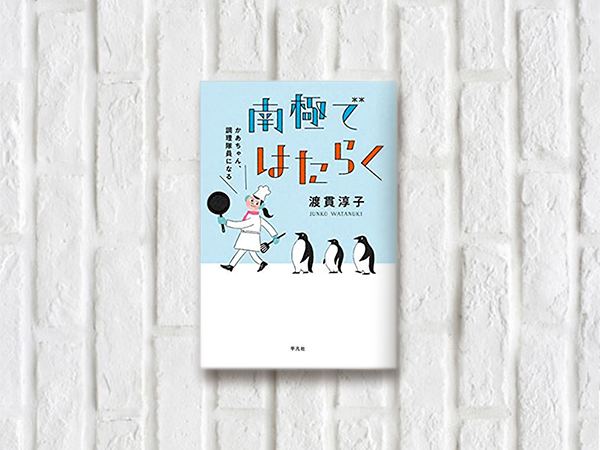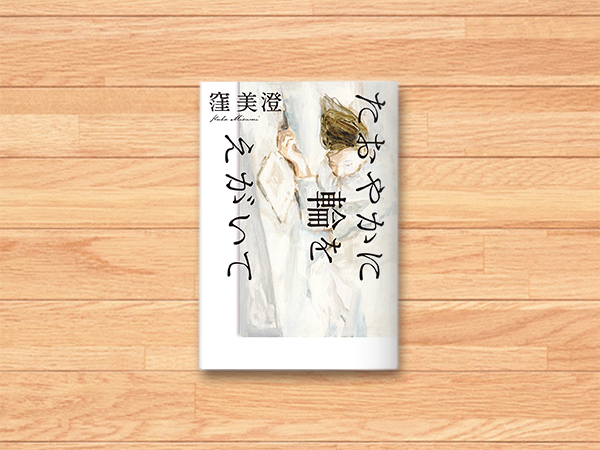その扉をたたく音(瀬尾まいこ)
 |
|
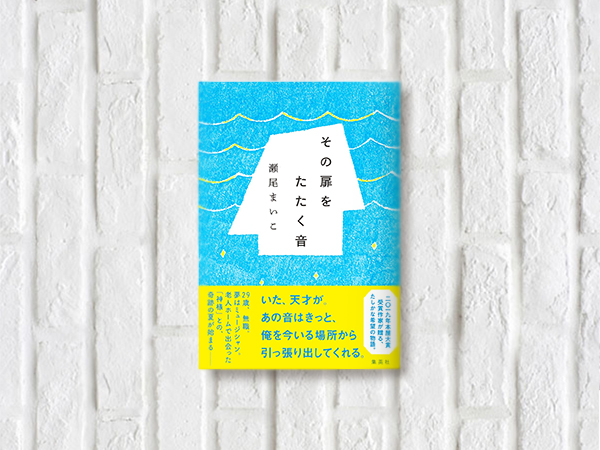 哀しくて爽やか その扉をたたく音
瀬尾まいこ(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。
今回ご紹介するのは、瀬尾まいこさんの『その扉を叩く音』。 自称ミュージシャン 宮路は今年の誕生日が来ると30歳になる。宮路がギターに出会ったのは高校一年生の時だった。仲間とバンドを作って演奏することが楽しかった。そのまま音楽を続け、みんなが就職活動をする時期になっても、宮路は一人、就職活動をしなかった。
自分には音楽の才能がある、とまでは思っていないが、タイミングや運がめぐってくれば、音楽に関わる仕事ができるのではないか……、そんな甘い考えで続けてきた。だが一度たりとも音楽でギャラをもらったことはない。老人ホームや病院でボランティアで演奏するのが精一杯で、その演奏でさえ、喜ばれているという実感がない。 30歳までにはなんとかしたいと思いながら、今日もまた、老人ホームで弾き語りをし、さっぱりウケなかった。しかし宮路はその老人ホームで、天才的なサックス演奏者を見つけた。その老人ホームで介護をしている渡部という職員の演奏はこれまで聞いたどんなサックスとも違ったのだ。渡部と組めば、音楽で世界が取れそうな気がする。宮路は渡部を口説くために、 足しげく老人ホームに通い始めた……。 (瀬尾まいこ さん『その扉をたたく音』の出だしを私なりに紹介しました)
自分の好きなことを仕事にしたい、そう思う子どもに対して、多くの親が言う言葉
「●●で食べていけるのか?!」 これまでは●●に入るのは「音楽」や「文学」が定番でしたが、YouTuberが職業になる時代においては、もっと幅広い職業が当てはまるかもしれません。 しかし、この小説の主人公 宮路の父は少し違いました。 そもそもギターを息子に買い与えたのが自分だという引け目からか、音楽の道に進みたいという息子を頭ごなしに叱ったりしません。 ところが、音楽の世界で芽が出ない上、働かない息子に対して、ある日告げるのです。 「この家から出て行ってくれ」と。 宮路の父は地方政治家。ブラブラと遊んでいる息子が家にいることはイメージダウンに繋がると判断したのだろうと、宮路は理解します。 普通ならここで、なんらかの職につき、自分で食べていく方法を探すものですが、宮路の父は息子のためにアパートを借りてくれた上に、月に20万円振り込んでくれるのでした。 子どもに甘い父親という見方もできますが、親子関係がバレない離れた場所に息子を追い出した、冷たい親と言えなくもありません。 とはいえ経済的に恵まれた境遇なので、宮路はずるずると音楽を続けているのですが、仕送り生活もすでに7年、本人も、このままで良いと思っているわけではありません。 かと言ってどうすれば良いのかわかっていない宮路が「天才サックス奏者」を口説くため、老人ホームに通い続けることで、変化していきます。 歳をとるということがどういうことなのかを目の当たりにして、自分の人生を見直すことになるのです。 誰もが必ず歳をとります。老いるということは、これまでできていたことができなくなることであり、大切な思い出を手放していくことでもある。 そして誰もが必ず死にます。これは誰も避けられないこと。知識として知っていても、身近な人、もしくは自分に起こったことでないと、実感はできないのかもしれません。 宮路は老人ホームで初めて、年配の人と関わり、「生きる」ことを自分ごととして考えることになるのでした。 普通ならもっと早く気づかなくてはいけないだろうに、宮路は相当なのんびり屋と言えるでしょう。だけど、なぜか嫌な感じがしません。 宮路の、遅まきながらの成長物語。物哀しくも爽やかな読後感が味わえます。ぜひ読んでみてください。 その扉をたたく音
瀬尾まいこ(著) 集英社 ミュージシャンへの夢を捨てきれないまま、怠惰な日々を送っていた宮路。ある日、演奏に訪れた老人ホームで、神がかったサックスの音を耳にする。吹いていたのは、ホームの介護士・渡部だった。「神様」に出会った興奮に突き動かされた宮路はホームに通い始め、やがて入居者とも親しくなっていく…。人生の行き止まりで立ちすくんでいる青年と、人生の最終コーナーに差し掛かった大人たちが奏でる感動長編。二〇一九年本屋大賞受賞作家が贈る、たしかな希望の物 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook