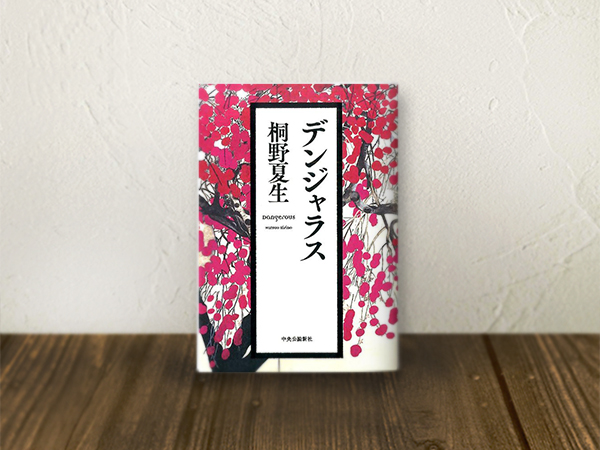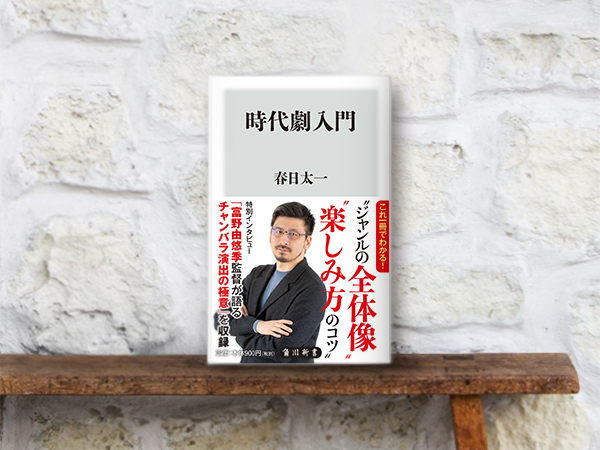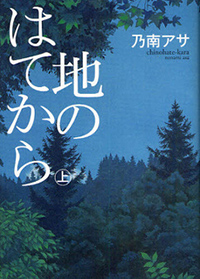Iの悲劇(米澤穂信 )
 |
|
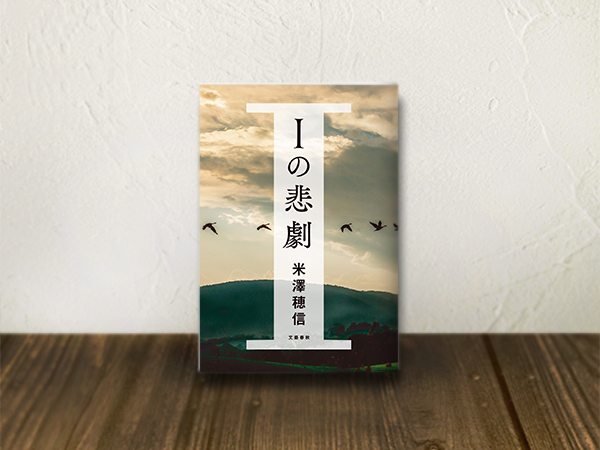 日本の各地にある「悲劇」かも Iの悲劇
米澤 穂信(著) 米澤穂信さんの『Iの悲劇』は、てっきりミステリだと思って読み始めたのに、全く違っていて、しかも面白い小説でした。
小説の舞台は人口6万人ほどの、南はかま市。その中の蓑石地区は、住民の高齢化による過疎が進み、6年前、ついに無人となった。
しかしこの度、新市長の肝いりで、蓑石地区再生のプロジェクトが始まった。新たな住民を呼び、定住してもらうことで、活気を取り戻そうという、いわゆる「Iターン」支援プロジェクトだ。 そのため南はかま市役所に特設されたのが「甦り課」。50歳過ぎの課長 西野秀嗣、三十歳手前の満願寺邦和、新人の観山遊香が配属された。 とは言え課長の西野は極力仕事をしたくなさそうだし、毎日定時には即居なくなる。観山は新人なので、ややこしい案件は任しきれない。結果的に、満願寺が一人で頑張ることが多い。 蓑石の再建プロジェクトに応募してきた移住希望者は年代も職業も、移住動機も様々な12世帯。中には癖のある人もいる。 「甦り課」は彼らから寄せられる要望や苦情をうまく捌けるのか?蓑石地区は甦るのか?! (米澤穂信さんの『Iの悲劇』の導入部分を私なりに紹介しました) 特設チーム「甦り課」に与えられた分室には一年中ストーブがあり、冬は雪かきが必須とのことなので、南はかま市はおそらく東北地方にあるのでしょう。
自然が豊かではあるものの、冬は厳しい、そんなに甘くない地域です。 そこに転居してきた人たちの動機は様々です。 「ラジコンヘリを思う存分飛ばしたい」 「近所に気兼ねなくアマチュア無線を楽しみたい」 「釣り三昧の生活をしたい」 といった、趣味が動機の人もいれば、 「子どもの健康のため」 「有害物質だらけの都会生活から逃れたい」 といった、健康上の理由の家庭もあれば、 「田舎だからできることで地域を盛り上げたい」 といった野心家も。 そんな彼らが住むことになるのは、住み手がいなくなった古い家ですから、あれこれ不便な点が出てきます。 また、気があう人と隣家になればいいけれど、そうでない場合もあり、そんな時彼らが頼るのは「甦り課」ということになります。 家族の数だけ、いえ、人の数だけ希望や苦情はあるもので、その度に「甦り課」職員が翻弄されるわけです。 「なるほど無理もない」と思える苦情もあるけれど、「困った人だな」と思うことが大半。 それに向き合わねばならないとは、市役所職員も大変だわねと、気の毒に思いながら読み進めました。 一番大変な思いをしているのは満願寺くんですが、いつもサボってばかりいる西野課長もいざという時はピシリと発言します。 また、頼りない新人だと思っていた観山さんが、意外とできる子だったりして、「甦り課」を応援する気持ちがどんどん強くなってきた終盤に、意外などんでん返しがあり、びっくり。 そういう話だったの?! と、驚くとともに「Iの悲劇」は”南はかま市”だけではなく、現代日本の各地で起こっている悲劇なのではないかと思いました。 Iの悲劇
米澤 穂信(著) 文藝春秋 一度死んだ村に、人を呼び戻す。それが「甦り課」の使命だ。人当たりがよく、さばけた新人、観山遊香。出世が望み。公務員らしい公務員、万願寺邦和。とにかく定時に退社。やる気の薄い課長、西野秀嗣。日々舞い込んでくる移住者たちのトラブルを、最終的に解決するのはいつもー。徐々に明らかになる、限界集落の「現実」!そして静かに待ち受ける「衝撃」。これこそ、本当に読みたかった連作短篇集だ。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook