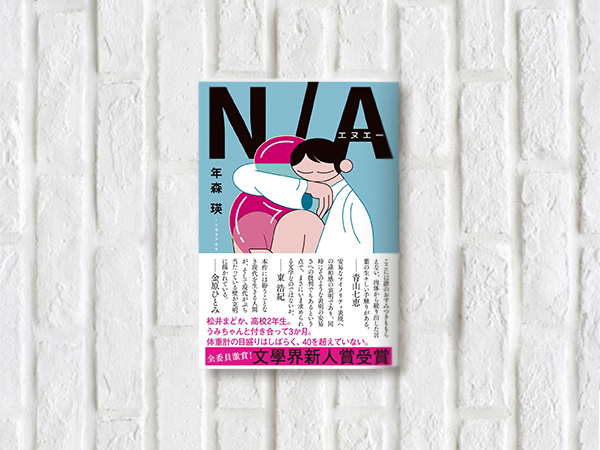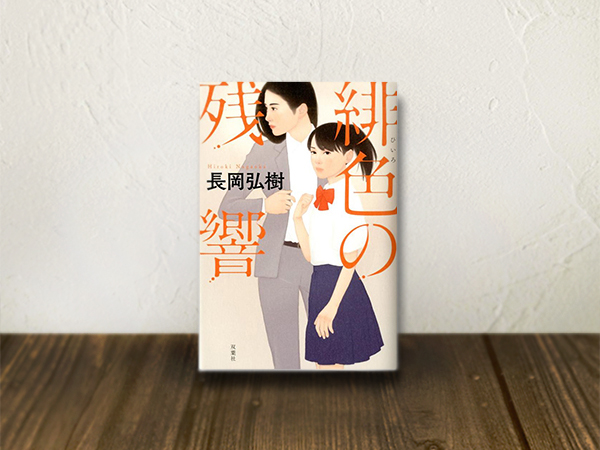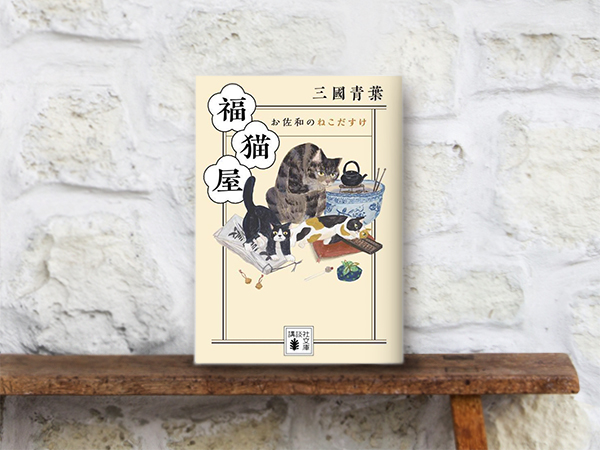貸出禁止の本をすくえ!( アラン・グラッツ)
 |
|
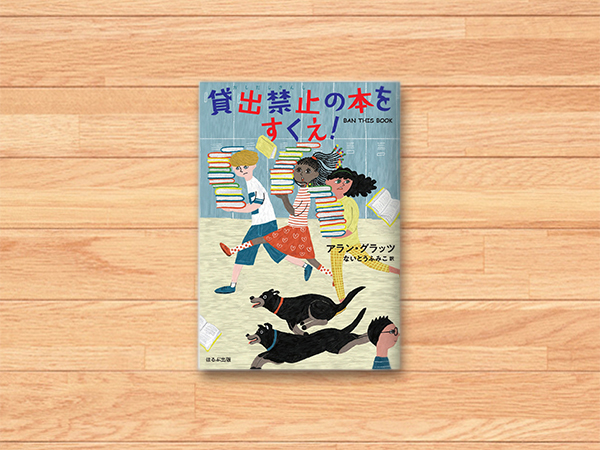 読書感想文にお勧めの一冊 貸出禁止の本をすくえ!
アラン グラッツ(著) 私がパーソナリティを担当している大阪府箕面市のコミュニティFMみのおエフエムの「デイライトタッキー」。その中の「図書館だより」では、箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介しています。
今回ご紹介するのは、アラン・グラッツ『貸出禁止の本をすくえ!』
エイミー・アンは本が大好きな9歳の女の子。パパとママ、二人の妹と、二匹の大型犬と住んでいる。
エイミー・アンは放課後はいつも図書室で本を読んで過ごす。本が大好きだから、だけではない。家に帰ると我慢しなければいけないことばかりだからだ。 部屋をシェアしているすぐ下の妹は、大音量の音楽をかけながらバレエの練習をしているし、下の妹はポニーになるのだと言って、エイミー・アンの本を勝手に持ち出して「柵」がわりにしたりする。 それを注意して喧嘩になると、いつも怒られるのはエイミー・アン。「お姉さんでしょ!」と。おまけに家の手伝いを頼まれるのはいつも自分ばかり。 大好きな本をゆっくり読む暇も場所もない、だからエイミー・アンは家に帰るのを遅らせるために、毎日図書室で過ごすのだ。 ところがある日、図書室に行ってみると、お気に入りの本が棚から消えていた。誰かが借りたからではなく、保護者の一人が「子どもが読むのにふさわしい本ではない」と言い出し、撤去しなくてはならなくなったという。 他にも色々な本が貸出禁止になっていた。それぞれ面白い本なのに、どうして読んではいけないの?! エイミー・アンは友だちと一緒に、 貸出禁止になった本をみんなが読めるように画策するのだった……。 (アラン・グラッツさんの『貸出禁止の本をすくえ!』の冒頭を私なりに紹介しました)
この物語のポイントは大きく二つ。
「これは読んでもいい本です」「これは子どもが読んではいけない本です」と、誰が決めるのか、そもそも決めていいのか、という問題。 現実世界でもオカルト的・悪魔的だということで『ハリーポッター』シリーズもクレームをつけられています。 実際に読んでみれば、友情の大切さを学べるし、冒険や挑戦のワクワクを感じられる素敵な作品なのに。 この物語の中で貸出禁止にされる本は、全て実在し、貸出禁止にされたことがある本ばかりなのだとか。 禁止にする理由の一つをあげてみると「うそつきや、ぬすみや、ずるのしかたをおしえる」から。 つまり、家を飛び出した少年少女が冒険の末自立するような物語は「家出を助長する本」という論理です。 だったら、推理小説のほとんどは強盗や殺人を助長したり、事件が起こること自体を面白がる、ひどい本ということになります。 そういえば、高見広春さんの『バトル・ロワイヤル』は第5回ホラー小説大賞にノミネートされたものの、中学生同士が殺しあいを強いられるという強烈なストーリーと、殺戮シーンのおぞましさから、選考委員にボロクソにけなされて受賞を逃したことがありました。 しかし、選考委員の反応のすごさが逆に「どんな作品なのか読んでみたい」と話題になり、出版される運びとなりました。 私も読んでみたのですが、本当におぞましい場面の連続なのに、最後の最後に「青春」と言おうか、若者の輝きと言おうか、自分でも説明ができないポジティブな印象を受けました。 そしてこれを最初から「読むべきではない」とは言えないなと思ったのです。 殺戮を描いた小説ですら、そう思うのです。ましてや、この本で貸出禁止にされた『スーパーヒーロー・パンツマン』などは、きっと上品な内容じゃないのだろうけど、いいじゃないの、読ませてあげてよ、と思わずにいられません。 その点については、エイミー・アンが信頼を寄せる図書室の司書ジョーンズさんの発言に言い尽くされていると思います。
「教育者としてのわたしたちのつとめは、子どもたちをできるかぎり多様な本、多様な視点にふれさせることです。
子どもたちにとって、やさしすぎる本も、むずかしすぎる本も、あるいは、うんと歯ごたえがある本も、ただ楽しいだけの本も、どうぞお読みなさいといってやることです。 そしてときには、わたしたちが賛成できないことがらが書かれた本を読むことを認めて、自分で考えさせることも必要です。 ハラハラすることもあるでしょう。ですが、それこそが良い教育なのではないでしょうか」 (アラン・グラッツ『貸出禁止の本をすくえ!』P39,P40より引用)
この物語のもう一つのポイントは、エイミー・アンの成長。
彼女は本好きで、頭の回転が早く、ボキャブラリーも豊富なのに、言いたいことを飲み込む癖があります。 それは友だちに対しても、家族に対しても。自分が発言することでどんな結果になるかを想像し、発言をしないことにしているのです。 「どうせ結果はこうなる、言っても無駄」という諦めの気持ちです。 そんなエイミー・アンが、貸出禁止になった本を救うため、クラスメートと知恵を出し合い、行動するようになって、成長していくのです。 私は大人なので、彼女たちを見守りながら読みましたが、同年代のお子さんなら、エイミー・アンと一緒に分からず屋の大人と戦う気分を味わえると思います。 特に、本が好きなお子さんや、妹や弟がいて、いつも少しずつ我慢をしているお子さんなら、エイミー・アンを自分のことのように思えるはず。読書感想文にお勧めの一冊です。 貸出禁止の本をすくえ!
アラン グラッツ(著) ほるぷ出版 わたし、エイミー・アン、9歳。家ではわがままな妹がやりたいほうだいで、おちつくのは図書室にいるときだけ。でもある日、お気に入りの本が棚から消えていた。いったいどうして? 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook