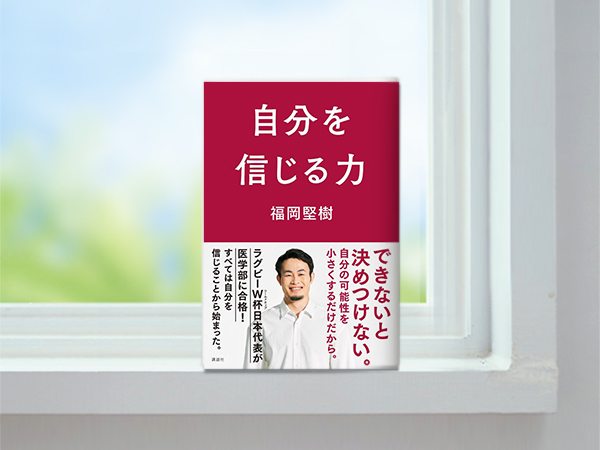家守綺譚(梨木香歩)
 |
|
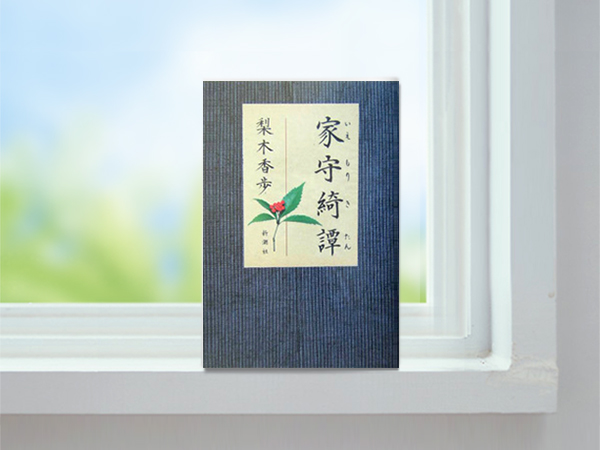 家守綺譚
梨木香歩(著) 『西の魔女が死んだ』で有名な梨木香歩さんですが、私は梨木さんの作品を読むのは初めてです。
『家守綺譚』は小説という体裁を取らず、 「左は、学士綿貫征四郎の著述せしもの。」
(冒頭より引用)
という冒頭の記述により、読者は綿貫の忘備録か日記を読んでいるかのような気持ちで読み進めることになります。
時代は明治。 はっきり地名は書かれていないものの、京都北部か滋賀県が舞台と思われます。 物書きを本分としている綿貫征四郎はそれ一本ではなかなか食べていけず、非常勤講師として英語学校に勤めている。先立つものがなく心細いところに、持ち込まれたのが「家守(いえもり)」の話。亡くなった友人 高堂の父が、高齢のため嫁に行った娘の近くに引っ越すのだという。ついては息子の友人だった綿貫に家を守って欲しいというのだ。
人の住まない家は荒れるというので、住んで窓の開け閉めなりとしてもらえれば…と思ったのだろう、家賃を取るどころか、逆に月々わずかではあるが謝礼もくれるとのこと。綿貫にとってはこれ以上の話があるはずはなく、快諾し、同時に英語学校も辞め、いよいよ文筆業に精を出す毎日となった。 預かった家には和風の庭がある。かなり広い庭なのか、シュロやクスノキ、キンモクセイ、サツキ、サザンカ、タイサンボク、槇、榊、柴、スギなどなど、植物がいっぱい植わっている上に池まである。高堂の父は定期的に植木屋に手入れをしてもらっていたらしいが、綿貫が住むようになってからはそれもなく、植物たちは元気一杯に育ち続け、それはそれで野趣溢れる風情を醸し出している。 ある大雨の日、不思議なことが起こった。水辺の風景を描いた掛け軸の画が動き出し、向こうからボートが近づいてくるではないか。漕ぎ手は死んだはずの高堂。しかも、高堂とは会話もできるのだった。高堂は庭のサルスベリの木について、不思議なことを言い置いて帰っていく。ーまた来るよ。との言葉を残して。 普通に考えれば、掛け軸の絵が動いて、亡き友人が現れたりしたら怪奇現象でしょう。
しかし、綿貫くんは怖がりません。 別れを告げることもなく、二度と会えなくなった友人が会いに来てくれたのかと、むしろ喜んでいるのです。 また、亡き友人との再会がきっかけであったかのように、不思議なことが次々と起こります。 疎水から池の庭に人魚が流れ着いたり、狸が化かしに来たり、河童の皮を拾ったり…。 一種のファンタジーですが、綿貫くんが淡々とそれを受け入れるので、こちらとしても、「まぁそんなこともあるかも…」なんて思ってしまうのがおもしろいです。 サルスベリ、都忘れ、ヒツジグサ、ダァリヤ…など28の植物のタイトルがついた掌篇集なので、すきま時間に読むのにぴったり。 とはいえ、どれもしっとりとした内容で、短くても読み応えは十分です。 タイトルが奇譚、ではなく綺譚とあるように、単に珍しい話ではなく、巧みで美しい話なのです。 もう一つ、綿貫くんの食事が、やたらと おいしそうなのが読んでいて楽しい。 たとえば、牛蒡と小芋、鰯の炊き合わせに麦飯とろろ とかまだ日の光を浴びていない白い筍を炭火であぶって焦げ目がついたところに鰹節と生醤油…とか、思わずゴクリとなってしまいます。 犬好きな私としては、ひょんなことから綿貫の家に居着くようになったゴローの活躍も嬉しい。 読み終わった時になぜか夏目漱石の随筆『硝子戸の中』を思い出すタイトルに負けない「綺譚」でした。 家守綺譚
梨木香歩(著) 新潮社(2004) たとえばたとえば。サルスベリの木に惚れられたり。床の間の掛軸から亡友の訪問を受けたり。飼い犬は河瞳と懇意になったり。白木蓮がタツノオトシゴを孕んだり。庭のはずれにマリア様がお出ましになったり。散りぎわの桜が暇乞いに来たり。と、いった次第の本書は、四季おりおりの天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon
|
OtherBook