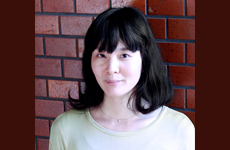HOME![]() ■シネマカフェ
■シネマカフェ
![]() [シネマトークレポート]大阪アジアン映画祭広報 音居あやさん
[シネマトークレポート]大阪アジアン映画祭広報 音居あやさん ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■シネマカフェ
[シネマトークレポート]大阪アジアン映画祭広報 音居あやさん

『映画祭のできるまで』
2018年1月25日に開催したシネマトーク、大阪アジアン映画祭広報担当の音居あやさんをゲストにお迎えしました。
大阪アジアン映画祭では、日本で初公開となるアジア各国の最新作映画が観られるとあって、たくさんの映画ファンを動員してきました。
ゲストと観客の交流の場を提供し、関西の映像制作人材の育成促進を図ってきた映画祭も今年で13回目。華やかな映画祭、その運営に携わる苦労と醍醐味を語っていただきました。

主婦バックパッカーが映画祭の広報に
現在音居さんは夫の転勤により名古屋在住で、映画祭の準備のため1月下旬から大阪に単身赴任しています。映画祭に関わるようになったきっかけを"ひょんなところから"という音居さん、当初ある会社の法務部に勤めていたそうです。
音居さん:約8年半勤めました。ストレスが溜まって3年ぐらい微熱を出しながら通っていましたが、これはいかんなと思いました(笑)
先の予定は全くないまま退職したのが32歳頃でした。1年海外を周り、2年目は中国に語学留学、3年目は3ヶ月ほどイギリスに滞在し、そのまま5ヶ月ほどヨーロッパを旅行しました。
主婦バックパッカーなんて言われながら色々回って(笑)。サラリーマンを離れるのは3年が限度かなと思って。
先の予定は全くないまま退職したのが32歳頃でした。1年海外を周り、2年目は中国に語学留学、3年目は3ヶ月ほどイギリスに滞在し、そのまま5ヶ月ほどヨーロッパを旅行しました。
主婦バックパッカーなんて言われながら色々回って(笑)。サラリーマンを離れるのは3年が限度かなと思って。
その後就職した国際会議の運営等を手掛ける会社は、2年ほど勤めて退社。そこで知り合った友人が大阪ヨーロッパ映画祭の広報を務めていて、広報のインターンを探してるという話を聞きました。
音居さん:気心の知れた人のそばでゆっくり働こうというのもあって、広報として入ったのが2009年の夏でした。
大阪アジアン映画祭に関わるようになったのはその翌年の2010年。暉峻創三さんがプログラミング・ディレクターとなった第1回目から広報を務めた友人の後任として音居さんに声が掛かり、広報に就任。その後経理も務めましたが、数年前からまた広報に戻りました。
岸野さん:何か参考になるんちゃうかな。向いてなければやめたらええねん(笑)。私は実は高校卒業して国家公務員をやったんですけど、限界になって3年で辞めました。
法律に則った書類を作るという仕事だったという岸野さん。辻褄合わせだけの仕事だと感じ、我慢できなかったと音居さんの行動に共感されました。
音居さん:友達に、今映画祭の仕事してるって言ったら、“ええっ、映画好きやったっけ?”って驚かれました。
映画のことを熱く語れるタイプではなく、大毎地下劇場という二本立ての映画館の会員になっていたとか、学生時代に『愛人/ラマン』を授業を休んで見に行ったとか、そんな程度です。
こんな私が広報でいいのかって思います(笑)。今も大して変わらないですが、大阪アジアンで上映する作品については詳しくなりました。
映画のことを熱く語れるタイプではなく、大毎地下劇場という二本立ての映画館の会員になっていたとか、学生時代に『愛人/ラマン』を授業を休んで見に行ったとか、そんな程度です。
こんな私が広報でいいのかって思います(笑)。今も大して変わらないですが、大阪アジアンで上映する作品については詳しくなりました。

大阪アジアン映画祭の誕生
大阪アジアン映画祭の第1回目は「韓国エンタテイメント映画祭2005 in大阪」として開催されました。
その後、「日本未公開の作品を主体にした映画祭をやろう」と新たな企画が立ち上がり、東京国際映画祭でアジア映画のプログラミング・ディレクターを務めていた暉峻創三さんが2009年から作品をセレクション。
現在では大阪市や一般社団法人大阪アジアン映画祭など7つの団体からなる大阪映像文化振興事業実行委員会が主催しています。
その後、「日本未公開の作品を主体にした映画祭をやろう」と新たな企画が立ち上がり、東京国際映画祭でアジア映画のプログラミング・ディレクターを務めていた暉峻創三さんが2009年から作品をセレクション。
現在では大阪市や一般社団法人大阪アジアン映画祭など7つの団体からなる大阪映像文化振興事業実行委員会が主催しています。

積み重ねてきた映画祭の実績
当初は映画祭の知名度がなく、上映作品の応募数も少なかったそうです。
音居さん:こちらからオファーしてもなかなか決まらなかったのが、4~5年ぐらい前から応募作のレベル自体が全体的に上がってきたように感じます。
台湾のウェイ・ダーション監督の『セデック・バレ』が観客賞を取ったことも影響したのではないでしょうか。あの映画祭は観客が見る目がある、ジョニー・トー監督が小さい映画祭やけど毎年出品してる、という噂や実績が積み重なったようです。
台湾のウェイ・ダーション監督の『セデック・バレ』が観客賞を取ったことも影響したのではないでしょうか。あの映画祭は観客が見る目がある、ジョニー・トー監督が小さい映画祭やけど毎年出品してる、という噂や実績が積み重なったようです。
以前なら絶対入選したというレベルの作品を外さざるを得なくなって来たほど作品が充実して来たといいます。

ちょっと気になる映画祭の台所事情
そもそも映画祭ってどこからお金が出ているのでしょうか。音居さんはそんな疑問にもバッチリ応えます。
音居さん:入場収入は全予算全体の20%弱ぐらいなんです。公式に発表されてますが、大阪市から約2000万円出していただいて、あとは、状況によって政府の海外に対するプロモーションで助成金が出たり、その年に特集上映のある国からの協賛金など、様々なところからどれだけもらえるかですね。
スケジュールは、早い映画祭なら3か月前くらいに決まります。プログラミング・ディレクターの暉峻は最大限待つ主義で、本当にギリギリに決めてくるんですよ。
スケジュールは、早い映画祭なら3か月前くらいに決まります。プログラミング・ディレクターの暉峻は最大限待つ主義で、本当にギリギリに決めてくるんですよ。
3月9日から開催の今年の映画祭では、2月頭にはウェブで作品名、メインのビジュアルと監督名と作品名を発表します。
チラシはフォーマットを用意してスタンバイ。チケットの発売が2月24日、その一週間前にはチラシを配ろうと動きますが、厳しいスケジュールになるため情報待ちの印刷物を作る担当者は大変です。広報としては、作品が決まった後の細かい交渉も山積みです。
チラシはフォーマットを用意してスタンバイ。チケットの発売が2月24日、その一週間前にはチラシを配ろうと動きますが、厳しいスケジュールになるため情報待ちの印刷物を作る担当者は大変です。広報としては、作品が決まった後の細かい交渉も山積みです。

映画祭を支えるボランティアスタッフの力
大阪アジアン映画祭は、有償で携わるスタッフの数は少ないとのこと。去年参加したボランティアスタッフは総数約140人。大きく分けてその仕事は3つあります。
1つ目は会場担当でもぎりや受付、劇場の中の案内係。2つ目がゲスト担当。ゲストホスピタリティと言って会場とホテル間の付き添いや会場での誘導など。そして3つ目が広報関連です。昨年は映画の上映が約103本、そのうち87本にゲストが来ました。その全てのゲストのトークとその様子を写真に撮り、ウェブで紹介する開催レポートという作業です。
1つ目は会場担当でもぎりや受付、劇場の中の案内係。2つ目がゲスト担当。ゲストホスピタリティと言って会場とホテル間の付き添いや会場での誘導など。そして3つ目が広報関連です。昨年は映画の上映が約103本、そのうち87本にゲストが来ました。その全てのゲストのトークとその様子を写真に撮り、ウェブで紹介する開催レポートという作業です。
音居さん:こんなにボランティアさんにお世話になってる映画祭ってあんまりないんじゃないですかね(笑)
他の映画祭だと、ボランティアさんにゴミ集めやお茶配りなどプラスアルファの仕事を任せてるところもありますが、大阪アジアンは、あなたがおらへんと困るねん!みたいな(笑)
他の映画祭だと、ボランティアさんにゴミ集めやお茶配りなどプラスアルファの仕事を任せてるところもありますが、大阪アジアンは、あなたがおらへんと困るねん!みたいな(笑)
音居さんはボランティアスタッフについてどんな方でもウエルカムだと語ります。
音居さん:映画が好きな方、ボランティア活動したいと思っている方、語学を使いたいと思ってるとか入り口は様々ですし、毎年参加のベテランさんから初めての方まで、皆さんそれぞれ自分の居心地のいい場所を見つけて頂いてますね。

求む!若い世代の観客たち
観客の女性から、お客さんの傾向の推移について質問が挙がりました。
音居さん:チケットぴあさんに委託しているので、最後に集計した購入者層を教えてもらえるんですけど、大体40歳くらいから1年毎に平均年齢が上がっている時期がありました。去年ちょっと止まったかな。男女比は、7︰3ぐらいで女性ですね。20本以上観るようなコアな人は20~30人ぐらいです。
去年、詳しいアンケートをウェブサイトで募り、全体の約5%が回答した中から割り出したところ、動員延べ人数は約1万人の中、実質約3000人~4000人の観客が来場したことが分かったそうです。
複数鑑賞する方は多いものの、1~2本の鑑賞にとどまる人で半数を超えてます。毎年、全体の約1/3が初めて映画祭に来た人の割合だそうです。
複数鑑賞する方は多いものの、1~2本の鑑賞にとどまる人で半数を超えてます。毎年、全体の約1/3が初めて映画祭に来た人の割合だそうです。
音居さん:22歳以下当日券500円って制度があるんですけど、あまり広がらないんですよ。映画館に行く人数自体は増えているから、日本映画のキャピキャピキュンキュンものや、ハリウッドものを観にくる人たちを捕まえるにはどうしたら?って悩んでます(笑)
岸野さんは、映画好きな人が率先して誘うべきだと指摘します。
岸野さん:自発的に映画館に行かない世代の人も多いじゃないですか。子供の頃から映画館に連れていくっていうのを大人がやらないと。映画館に行くという行為自体が自分の生活のサイクルに入ってない人を呼び込むのは、よほどのきっかけがないと難しいですよ。
休みにプライベートで海外の映画祭にふらっと出掛けるという音居さん。たくさんの若いお客さんたちが当日券を求めて並んでいることに驚くそうです。
また、テレビの特集で海外の映画祭に来た地元の若いお客さんが「毎年この映画祭で上映される作品なら時間が合えば何でも観ている」と答える姿を見て、映画祭が地域に根付いている様子にこの違いはなんだろうと考えるそうです。
また、テレビの特集で海外の映画祭に来た地元の若いお客さんが「毎年この映画祭で上映される作品なら時間が合えば何でも観ている」と答える姿を見て、映画祭が地域に根付いている様子にこの違いはなんだろうと考えるそうです。
音居さん:知らないっていうのは大きいかもしれないですね。私の周りでも“映画祭ってなに?”みたいな(笑)
岸野さん:知らないものを観る好奇心を養って欲しいですね。思わぬ掘り出し物があるし、発見したその人の宝物になるしね。

新しい才能の育成や、地域おこしという役割
音居さん:暉峻が気にかけていることの一つが、世の中に知られてない才能を発掘するということです。世界初上映の作品や海外のまだ知られてない監督の作品を紹介したり、日本映画の若手も掘り出して逆に海外に伝えると言うことも映画祭の使命だと思っています。
映画祭と連動して、13年間映画制作者を育ててきたCO2(シネアストオーガニゼーション大阪)からも様々な作品が生まれました。CO2は昨年度をもって独立したため今後の活動も注目したいところです。
岸野さん:監督の横浜聡子さんや西尾孔志さんもCO2の出身ですね。結構いい作品もあって、3年前には私の大好きな草野なつかさんの『螺旋銀河』が一般公開され、今年は藤村明世さんの『見栄を張る』という作品が公開予定(3月24日)です。
香港で制作された『十年』というオムニバス映画がありました。この先の10年に危機感を持った世代の監督たちが作った作品なんですけど、今度是枝裕和監督が取りまとめ役になって、アジア全体で『十年』を作ることになり、藤村さんはその一人に選ばれました。
映画の発見もそうですけど、映画祭が新しい才能を育てるってっていう役割もあるわけですね。
香港で制作された『十年』というオムニバス映画がありました。この先の10年に危機感を持った世代の監督たちが作った作品なんですけど、今度是枝裕和監督が取りまとめ役になって、アジア全体で『十年』を作ることになり、藤村さんはその一人に選ばれました。
映画の発見もそうですけど、映画祭が新しい才能を育てるってっていう役割もあるわけですね。
司会の千葉さんから「地域おこしという観点から、成果は出ていますか?」との質問が。
映画祭で来阪する人が増えたか、明確なデータはまだないそうです。それでは映画祭がきっかけで、アジアの映画人が大阪をロケ地に選ぶといったケースはあるのでしょうか?
映画祭で来阪する人が増えたか、明確なデータはまだないそうです。それでは映画祭がきっかけで、アジアの映画人が大阪をロケ地に選ぶといったケースはあるのでしょうか?
音居さん:そうですね。ロケ地に関しては私も詳しくは知らないんですけど、撮る側も迎える側もお互いが魅力を感じ合わないと成立しませんよね。
2月公開のジョン・ウー監督の『マンハント』は、 大阪アジアン映画祭は関わってないけど、あぁっ!と言うような見慣れた大阪の風景や場所が出てきますよ。
2月公開のジョン・ウー監督の『マンハント』は、 大阪アジアン映画祭は関わってないけど、あぁっ!と言うような見慣れた大阪の風景や場所が出てきますよ。

新しい価値観との出会いが待っている映画祭
岸野さん:やっぱりしんどいけど楽しいと思える人じゃないとできないですよね。苦労はあるけど、こういうことがあるからやめられへんのよねという醍醐味はありますか?
音居さん:よかったエピソードで言うと、 今まで作品を観て来て一番好きなのがマレーシアの『タレンタイム』。
数年前に亡くなった監督で、少し前に劇場でも一般公開されたんですけど、これは映画祭に関わってなかったら観てなかったなーと思います。仕事としてはおもしろいですが、ただこれで生活をしていこうと思うと大変やと思います。
数年前に亡くなった監督で、少し前に劇場でも一般公開されたんですけど、これは映画祭に関わってなかったら観てなかったなーと思います。仕事としてはおもしろいですが、ただこれで生活をしていこうと思うと大変やと思います。
東京在住で映画祭関連の仕事をしている人は、映像関係や映画祭関係の仕事を掛け持ちしながら生活をすることが出来るようですが、関西ではなかなか厳しいとのこと。毎年スタッフを探すのも苦労するといいます。
音居さん:かなりの部分を1人ひとりに任せる状況になるので、映画祭で時間を掛けて育てるのができないのが辛いところです。
2年前の思い出話も飛び出します。『湾生回家』の宣伝担当になった岸野さん。関係者が帰った後に観客賞受賞が発表され、東京の配給会社から代わりに受賞式に出るよう頼まれ登壇しました。
副賞はスポンサーの薬師真珠提供の真珠のネックレスでしたが、観客席にそれを見せようとしたとたん、固定していなかったネックレスがケースからポロンと落ちるアクシデントが・・・。
副賞はスポンサーの薬師真珠提供の真珠のネックレスでしたが、観客席にそれを見せようとしたとたん、固定していなかったネックレスがケースからポロンと落ちるアクシデントが・・・。
音居さん:いろんな方にすみませんって、そんなことがありましたね(笑)
岸野さん:その後ちゃんと台湾の監督にお渡ししましたからね(笑)
映画祭のエピソードはつきませんが、今年も様々なドラマが生まれたことでしょう。
観光旅行とは違った観点で様々な国の文化や人、価値観に出会える映画祭。大阪アジアン映画祭に限らず、各地の映画祭、映画祭に関するイベントなど、新しい価値観の世界に触れてみてはいかがでしょうか。
観光旅行とは違った観点で様々な国の文化や人、価値観に出会える映画祭。大阪アジアン映画祭に限らず、各地の映画祭、映画祭に関するイベントなど、新しい価値観の世界に触れてみてはいかがでしょうか。
ゲストプロフィール

音居あやさん
ひょんなことからこの世界に入ることになり、2009年大阪ヨーロッパ映画際で広報インターン。その後、2010年(第6回大阪アジアン映画祭。暉峻創三プログラミング・ディレクター 2年目)大阪アジアン映画祭広報担当。翌年から経理などもろもろを担当した後、2013年に再び広報担当。現在に至る。その他、2011年から2017年、東京国際映画祭でカタログなどの校正を担当。MC

岸野令子
映画パブリシスト/有限会社キノ・キネマ代表。主にミニシアター向け映画の宣伝・配給担当。 FB: reiko.kishino

千葉 潮
合同会社メディアイランド代表。女性と子ども応援を理念に、教育、教材、一般書の発行、編集サービスを行なう。http://www.mediaisland.co.jp/レポーター

松田洋子
(デューイ松田)
小学4年生の頃、叔母に連れられて『ゾンビ』『オーメン2』の2本立てを観たことからジャンル映画に魅せられる。アニメーター、イラストレーターを経て、2009年より「デューイ松田」名義で映画関係のフリーライターとして活動。ゆうばり国際ファンタスティック映画祭、プチョン国際ファンタスティック映画祭、CO2の取材記事や大阪アジアン映画祭の記録撮影など。(デューイ松田)
■シネマカフェ 記事一覧
-
2018年1月は大阪アジアン映画祭広報担当、音居あやさんをお迎えしました
-
2017年11月は映画宣伝プロデューサーの松井寛子さんをゲストにお迎えしました
-
2017年9月は大阪・ミナミにあるミニシアター「シネマート心斎橋」支配人、横田陽子さんをゲストにお迎えしました
-
2017年7月は神戸・元町商店街にあるミニシアター「元町映画館」支配人、林 未来さんをお招きしました
-
2017年5月は大阪九条のミニシアター「シネ・ヌーヴォ」支配人、山崎紀子さんをゲストにお迎えしました