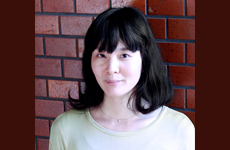HOME![]() ■シネマカフェ
■シネマカフェ
![]() [シネマトークレポート]映画宣伝プロデューサー 松井寛子さん
[シネマトークレポート]映画宣伝プロデューサー 松井寛子さん ![]() 前のページへ戻る
前のページへ戻る
■シネマカフェ
[シネマトークレポート]映画宣伝プロデューサー 松井寛子さん

『映画宣伝の”あれこれ”を語る』
2017年11月20日に開催したシネマトークのゲストは、映画宣伝プロデューサーである松井寛子さん。長い間、関西の映画業界に携わってこられたお二人が語る関西映画宣伝事情の”あれこれ”。果たしてどんなお話が飛び出したのでしょうか?

晴れた日は外に出たい映画宣伝プロデューサー
 松井さん:私も長いですが、岸野さんのほうが映画についてはよくご存じですね。私は天気のいい日は外に出たいタイプで、こんないい天気なんだから、散歩に出たり山へ登ったりした方がいいのに、なんで映画館みたいな暗いところへ行くんだろう、と思うことがあるんですね(笑)。反対にお客さんにはありがたいなと思いますけど。
松井さん:私も長いですが、岸野さんのほうが映画についてはよくご存じですね。私は天気のいい日は外に出たいタイプで、こんないい天気なんだから、散歩に出たり山へ登ったりした方がいいのに、なんで映画館みたいな暗いところへ行くんだろう、と思うことがあるんですね(笑)。反対にお客さんにはありがたいなと思いますけど。気さくな大阪のおばちゃんといった雰囲気でハツラツと自己紹介を始める松井寛子さん。休日は完全に映画のことを忘れて、散歩やお寺めぐり、展覧会などに行かれるそうです。大阪は映画ファンが少ないことを実感されていて、映画宣伝で重要なのは“口コミ”だと仰います。
その例として松井さんが挙げたのは、2017年のドキュメンタリーの大ヒット作品『人生フルーツ』(監督:伏原健之)。元建築家の老夫婦が自然と共に生きる生活を描いた作品で、好評につきアンコール上映が始まる映画館もあり大ヒットとなりました。
その例として松井さんが挙げたのは、2017年のドキュメンタリーの大ヒット作品『人生フルーツ』(監督:伏原健之)。元建築家の老夫婦が自然と共に生きる生活を描いた作品で、好評につきアンコール上映が始まる映画館もあり大ヒットとなりました。
 松井さん:ドキュメンタリーでこれだけ入るって、たぶん、1987年の『ゆきゆきて神軍』(監督:原一男)を超えてるんですね。最初のうちは新聞やTVで紹介されるんですけど、そういった情報がなくなっても、FacebookやTwitter で友達が、“この映画はいいよ”って言ったら、やっぱりお客さんは観に行きはるんですよ。
松井さん:ドキュメンタリーでこれだけ入るって、たぶん、1987年の『ゆきゆきて神軍』(監督:原一男)を超えてるんですね。最初のうちは新聞やTVで紹介されるんですけど、そういった情報がなくなっても、FacebookやTwitter で友達が、“この映画はいいよ”って言ったら、やっぱりお客さんは観に行きはるんですよ。『人生フルーツ』は幅広い年代の男女に関心を持たれ、大ヒットとなりました。一方、男性は一人で映画館に行く方が多いようで、男性向けの映画はなかなか動員に結びつかないそうです。ところがそうしたセオリーを破ったのが2016年に公開された『ヤクザと憲法』(監督:土方宏史)という作品です。
この映画は、大阪の指定暴力団事務所に入り込んで撮影された、東海テレビドキュメンタリー劇場第8弾の作品。男性客だけでなく女性やカップルなど意外な動員に結びつき、これも大ヒットとなりました。実はヤクザや警察も劇場に観に来ていたと言う裏話も。
この映画は、大阪の指定暴力団事務所に入り込んで撮影された、東海テレビドキュメンタリー劇場第8弾の作品。男性客だけでなく女性やカップルなど意外な動員に結びつき、これも大ヒットとなりました。実はヤクザや警察も劇場に観に来ていたと言う裏話も。
 松井さん:ヤクザの世界ってどんな映画かなって誰でも興味あるじゃないですか(笑)。警察の人もいっぱい観に来てるから絶対安全やし、こんな映画見たことないやろ?って(笑)。いろんな人に観に来てもらって、おかげさまで大ヒットしました。いい映画には力がある。それをちょっと手助けするのが私たちの役目やと思うんです。
松井さん:ヤクザの世界ってどんな映画かなって誰でも興味あるじゃないですか(笑)。警察の人もいっぱい観に来てるから絶対安全やし、こんな映画見たことないやろ?って(笑)。いろんな人に観に来てもらって、おかげさまで大ヒットしました。いい映画には力がある。それをちょっと手助けするのが私たちの役目やと思うんです。そして「映画はやっぱり映画館で観てほしい。家のテレビで見るのと、映画館のスクリーンで観るのとでは、集中力が全然違う!」と熱っぽく語る松井さんでした。

映画ではなく“人”に変えられた松井さんの人生
岸野さんから「人生を変えた映画を挙げてもらえますか?」と質問を受けた松井さん。「それが無いんです」という意外な答えが。
 松井さん:生身の人間に変えられたほうが多いですね。小川紳介監督、黒木和雄監督、プロデューサーの前田勝弘さん、土本典昭監督。彼らと話していると、最初は全然理解できなかったんです。まだ私も若かったから必死になって、どういうことを言ってはるんやろ?と一生懸命聞くし、そのうちにふと腑に落ちてくる。本当にいい人たちに出会ってきたなと思います。
松井さん:生身の人間に変えられたほうが多いですね。小川紳介監督、黒木和雄監督、プロデューサーの前田勝弘さん、土本典昭監督。彼らと話していると、最初は全然理解できなかったんです。まだ私も若かったから必死になって、どういうことを言ってはるんやろ?と一生懸命聞くし、そのうちにふと腑に落ちてくる。本当にいい人たちに出会ってきたなと思います。だからこそ若い人には、いい作家と出会うようにとアドバイスされるそうです。
ところで、映画宣伝に携わるお二人ですが、松井さんの肩書きは“映画宣伝プロデューサー”。岸野さんは“映画パブリシスト”という肩書き。この違いについてお話いただきました。
松井さんは、一つの配給会社と長い付き合いがあり、自分の名前が出なくても、企画段階から作品に関わることがあるためこの肩書きを使っているとか。作品を編集の段階で見せてもらうこともあり、この作品はこの媒体が向いているとアドバイスをすることもあるそうです。
ところで、映画宣伝に携わるお二人ですが、松井さんの肩書きは“映画宣伝プロデューサー”。岸野さんは“映画パブリシスト”という肩書き。この違いについてお話いただきました。
松井さんは、一つの配給会社と長い付き合いがあり、自分の名前が出なくても、企画段階から作品に関わることがあるためこの肩書きを使っているとか。作品を編集の段階で見せてもらうこともあり、この作品はこの媒体が向いているとアドバイスをすることもあるそうです。
 松井さん:『ある精肉店のはなし』(監督:纐纈あや)もそうだし、ドキュメンタリーが結構多いんですよね。最初の段階から予算を聞いて、これやったらこうしましょうか、みたいな感じで進めていきます。
松井さん:『ある精肉店のはなし』(監督:纐纈あや)もそうだし、ドキュメンタリーが結構多いんですよね。最初の段階から予算を聞いて、これやったらこうしましょうか、みたいな感じで進めていきます。一方、岸野さんは、もともと全大阪映画サークル協議会の事務局に勤めておられましたが、1989年に退職しフリーに。当時は大阪にもミニシアターが開設しはじめましたが、まだ関西に配給会社の支社が無い時代でした。そこで、関西での上映時に宣伝する人がいないという事情と、映画宣伝の仕事に興味があった岸野さんの希望がぴたりと一致。
 岸野さん:宣伝広報をする人をパブリシストっていうものですから、映画の宣伝屋さんっていうことで、“映画パブリシスト”と名乗りました。
岸野さん:宣伝広報をする人をパブリシストっていうものですから、映画の宣伝屋さんっていうことで、“映画パブリシスト”と名乗りました。最初は北浜の三越劇場を中心に映画の宣伝に取り組まれた岸野さん。
 岸野さん:私が持ってきて一番最初に大ヒットしたのが、パトリス・ルコント監督の『髪結いの亭主』です。まだ有名な監督じゃなかったんですけど、91年に大ヒットして恋愛映画のルコントと言われるようになりました。
岸野さん:私が持ってきて一番最初に大ヒットしたのが、パトリス・ルコント監督の『髪結いの亭主』です。まだ有名な監督じゃなかったんですけど、91年に大ヒットして恋愛映画のルコントと言われるようになりました。宣伝の相談を受けた当時、日本語字幕も入り、公開の準備が整っていたにも関わらず、配給会社側は、観客が来てくれるかどうか確信が持てない状況だったそうです。しかし絶対入るという予感がした岸野さん。
“これは賭けてもいい映画”だと、岸野さんも出資し共同配給として上映したところ大ヒット。その後もフランス映画の上映で多くのファンを集めた三越劇場でしたが、阪神淡路大震災を機に休館し、1995年に閉館となりました。
現在、アジア圏の映画宣伝に携わることが多い岸野さんですが、個人的には、ヨーロッパ映画の、冷たく人を突き放すような救いのない映画が好きとのこと。
“これは賭けてもいい映画”だと、岸野さんも出資し共同配給として上映したところ大ヒット。その後もフランス映画の上映で多くのファンを集めた三越劇場でしたが、阪神淡路大震災を機に休館し、1995年に閉館となりました。
現在、アジア圏の映画宣伝に携わることが多い岸野さんですが、個人的には、ヨーロッパ映画の、冷たく人を突き放すような救いのない映画が好きとのこと。
 岸野さん:今の、あまりにもハリウッド映画に偏っている状況はすごく嫌なんです。世界には何百と国があって、そこにいろんな民族がいて、それぞれが映画を作ってるわけです。そういう世界の映画をできるだけ多く日本で紹介したいという想いで今にいたりますね。
岸野さん:今の、あまりにもハリウッド映画に偏っている状況はすごく嫌なんです。世界には何百と国があって、そこにいろんな民族がいて、それぞれが映画を作ってるわけです。そういう世界の映画をできるだけ多く日本で紹介したいという想いで今にいたりますね。一方松井さんは、小川プロダクションの『ニッポン国古屋敷村』(監督:小川紳介)や、土本典明監督作品など、多くのドキュメンタリー映画に関わってこられました。
現在、大型の劇場で上映される映画は、ほとんどオリジナル作品がなくなっています。漫画原作やスターの出演を前提とした企画、製作委員会を作ってリスク分散をするといった、メジャー映画の状況を横目に、松井さんはドキュメンタリーや作家性の強い映画にこだわります。
現在、大型の劇場で上映される映画は、ほとんどオリジナル作品がなくなっています。漫画原作やスターの出演を前提とした企画、製作委員会を作ってリスク分散をするといった、メジャー映画の状況を横目に、松井さんはドキュメンタリーや作家性の強い映画にこだわります。
 松井さん:ドキュメンタリーとか、売れている役者が出ていなくても本当に作家が作りたい映画、それを上映できるのは、やっぱりミニシアターができたからだと思うんですね。いろんな冒険ができるようになった。だからこそ宣伝には、新聞やテレビもですけど、やっぱり口コミがすごく大事です。今もそう思います。
松井さん:ドキュメンタリーとか、売れている役者が出ていなくても本当に作家が作りたい映画、それを上映できるのは、やっぱりミニシアターができたからだと思うんですね。いろんな冒険ができるようになった。だからこそ宣伝には、新聞やテレビもですけど、やっぱり口コミがすごく大事です。今もそう思います。
取り組む意義がある作品に惚れ込む
自身が手掛ける映画のこだわりについて岸野さんは、入らないとわかっていても、上映する意義があると思える映画が好きだと仰います。動員が少ないと読むならそれに見合う形で上映すべきだと。
 岸野さん:映画はただでさえ多様性の無いほうになびいているので、ヒットするものばかり並べてしまったら、これまでにないような映画が落ちこぼれてしまうわけです。観たらビビっとくる人は絶対いるはずなんですね。作り手の思いが見える作品に出会ったら応えてあげたい。
岸野さん:映画はただでさえ多様性の無いほうになびいているので、ヒットするものばかり並べてしまったら、これまでにないような映画が落ちこぼれてしまうわけです。観たらビビっとくる人は絶対いるはずなんですね。作り手の思いが見える作品に出会ったら応えてあげたい。それが結果的に入れば良しだけど、大ヒットしなかったとしても、映画に反応してくれた人がいることが、人にとって大きな知的財産だと思うんです。それはお金には変えられないから、ついつい入らないほうに(笑)
松井さんも同感で、
 松井さん:例えば一本宣伝して100万円になるなら、どんな作品でも折り合いつけようかと思うけど(笑)。現実はそうではないから、入らなくてもこの作品この人と一緒にやりたい、仮に赤字になっても良かったと思える映画を手掛けるようにしています。会社ならそういう訳にいかへんと思うので、ある意味、私は自分でプロではなくアマチュアだと思ってます。それは本も一緒だと思うんですね。
松井さん:例えば一本宣伝して100万円になるなら、どんな作品でも折り合いつけようかと思うけど(笑)。現実はそうではないから、入らなくてもこの作品この人と一緒にやりたい、仮に赤字になっても良かったと思える映画を手掛けるようにしています。会社ならそういう訳にいかへんと思うので、ある意味、私は自分でプロではなくアマチュアだと思ってます。それは本も一緒だと思うんですね。それを受けて、司会の千葉さんは、
 千葉さん:お客さんからの要望で出版する仕事も受けますけど 私の場合はメーカーでもあるので、これは自分で出さなアカンなと思った本は、売れなくても出すことがあって本当に苦しいです(笑)。
千葉さん:お客さんからの要望で出版する仕事も受けますけど 私の場合はメーカーでもあるので、これは自分で出さなアカンなと思った本は、売れなくても出すことがあって本当に苦しいです(笑)。企業の経営者が出す本では、社長の裸一貫出世物語では自慢話にしかならないので、伝えたいことを聞き、素材をどのように料理するかがポイントだそう。自分が惚れ込んだ人には時間もお金も費やしたいと話す千葉さん。そのマインドは松井さん、岸野さんとも共通するようです。

恩人の介護のために作った「風まかせ」
松井さんは現在、居酒屋「風まかせ」を運営されています。そのきっかけは映画の宣伝のためではなく、『サード』(監督:東陽一)のプロデューサーである前田勝弘さんが脳梗塞で倒れ、その介護のために始められました。
 松井さん:私は前田勝弘さんに、生き方や映画の自主上映のやり方とか全部を教わっているんです。しょうもないことも含めて(笑)。自主上映の赤字を負担する不安を漏らした時、“大阪の府民はどれだけいてると思ってるんや。大人は200万人がいるんやから、それだけおったらどないかなるやろ”って言われて目から鱗でした。
松井さん:私は前田勝弘さんに、生き方や映画の自主上映のやり方とか全部を教わっているんです。しょうもないことも含めて(笑)。自主上映の赤字を負担する不安を漏らした時、“大阪の府民はどれだけいてると思ってるんや。大人は200万人がいるんやから、それだけおったらどないかなるやろ”って言われて目から鱗でした。前田さんが脳梗塞で倒れた時、家族も離れていて見る人がいない状態でした。今と違って介護保険もなく社会全体で支えるものという意識がなかった時代。そんな時、松井さんが観た映画が『ある老女の物語』(監督:ポール・コックス)。政府が自宅介護の支援を積極的に行っているオーストラリアを舞台にした看護師と一人暮らしの老女との物語でした。
 松井さん:映画を観て感動して、これは実践しないと!と思って。前田さんのリハビリも兼ねて皆で集まる場所として、1997年に友人と共同で居酒屋「風まかせ」を始めました。
松井さん:映画を観て感動して、これは実践しないと!と思って。前田さんのリハビリも兼ねて皆で集まる場所として、1997年に友人と共同で居酒屋「風まかせ」を始めました。前田さんを迎えるために、本を読んで学習し、友達の力を借りて実践しつつ介護に当たった松井さん。
 松井さん:お金っていうのは、本気でやりたいと思ったら集まるもんやと思っています。生活以外はね。そんな感じで今日に至ってます。
松井さん:お金っていうのは、本気でやりたいと思ったら集まるもんやと思っています。生活以外はね。そんな感じで今日に至ってます。居酒屋「風まかせ」では2001年から月一回、映画の会を行っています。先にお題になる映画を決めて、その映画をどう思うか、10~15人ほどの集まったお客さんで意見をぶつけ合います。
 松井さん:一本の映画見たときに障害者の立場から見る人、歴史から観る人とか色々あるんですね。連合赤軍の映画の時は、それぞれ学生時代に共産党の人、全共闘の人もいてはるから見方が違う。その場では戦うんですけども、あとはケロッとしてまた仲良くなる。みんな映画の見方を刺激されるって言ってくれるんで今日に至るまで続いてるんですね。
松井さん:一本の映画見たときに障害者の立場から見る人、歴史から観る人とか色々あるんですね。連合赤軍の映画の時は、それぞれ学生時代に共産党の人、全共闘の人もいてはるから見方が違う。その場では戦うんですけども、あとはケロッとしてまた仲良くなる。みんな映画の見方を刺激されるって言ってくれるんで今日に至るまで続いてるんですね。底抜けに明るい松井さんの人柄がたくさんのお客さんを惹きつける様子が見えるようです。

女性の社会進出とミニシアターの関係
お二人は実は70年代に中之島公会堂で行われた『女ならやってみな』(監督:メッテ・クヌッセン)というデンマーク映画の自主上映に一緒に携わっています。
当時沸き上がったフェミニズム運動、その頃の日本では「ウーマンリブ」と呼ばれていましたが、女性達が自分たちの視点で観る映画の上映をやろうという企画のひとつで、普段男の人が行っている役割を逆転させてみたらという発想の映画でした。全国で自主上映会が行われ、お二人は大阪上映の実行委員会を一緒にされたそうです。
岸野さんが映画サークルの事務局を辞めてフリーになった後、映画ライターも考えられたそうですが、あまり需要が無かったため、関西の松竹系の洋画専門の子会社である松竹富士にアルバイトで入ることとなりました。当時の松竹富士の宣伝部は男性ばかり。そこに来たのが『赤毛のアン』(監督:ケヴィン・サリヴァン)でした。
当時沸き上がったフェミニズム運動、その頃の日本では「ウーマンリブ」と呼ばれていましたが、女性達が自分たちの視点で観る映画の上映をやろうという企画のひとつで、普段男の人が行っている役割を逆転させてみたらという発想の映画でした。全国で自主上映会が行われ、お二人は大阪上映の実行委員会を一緒にされたそうです。
岸野さんが映画サークルの事務局を辞めてフリーになった後、映画ライターも考えられたそうですが、あまり需要が無かったため、関西の松竹系の洋画専門の子会社である松竹富士にアルバイトで入ることとなりました。当時の松竹富士の宣伝部は男性ばかり。そこに来たのが『赤毛のアン』(監督:ケヴィン・サリヴァン)でした。
 岸野さん:『赤毛のアン』なんて男性はみんな理解できないって感じやったから、何言ってるんですか。これ絶対入ります。女の子はみんな『赤毛のアン』を読んでるんやから!って(笑)。それで好きに宣伝をさせてもらったんですね。大手の宣伝の仕方も学んで、新聞広告は毎週違う物を打って。すると89年に大ヒットしましたね。
岸野さん:『赤毛のアン』なんて男性はみんな理解できないって感じやったから、何言ってるんですか。これ絶対入ります。女の子はみんな『赤毛のアン』を読んでるんやから!って(笑)。それで好きに宣伝をさせてもらったんですね。大手の宣伝の仕方も学んで、新聞広告は毎週違う物を打って。すると89年に大ヒットしましたね。 松井さん:当時はオッサンたちが興行界を握ってたから価値観が違うんですよ。私たちは、これは絶対入る!と思ってるのに、オッサンたちはわからないんですよね(笑)。そういうことって長いことあったよねえ。
松井さん:当時はオッサンたちが興行界を握ってたから価値観が違うんですよ。私たちは、これは絶対入る!と思ってるのに、オッサンたちはわからないんですよね(笑)。そういうことって長いことあったよねえ。今は女性の映画監督がいっぱいいるけど、当時は羽田澄子さんとか松井久子さんとか、女性監督っていうだけで売りになってたしね。
 岸野さん:ミニシアターがたくさんできた契機のひとつに、女性の観客の『こういう映画が見たい』という要求があったんだと思います。東京の劇場がミニシアターを作り始めた時、支配人が女性だったり、配給会社も女性が働くようになって、女性が観たい映画がわかるようになってきた。それまで男性が買ってきたものとは違うテイストのものを上映し始めたんです。
岸野さん:ミニシアターがたくさんできた契機のひとつに、女性の観客の『こういう映画が見たい』という要求があったんだと思います。東京の劇場がミニシアターを作り始めた時、支配人が女性だったり、配給会社も女性が働くようになって、女性が観たい映画がわかるようになってきた。それまで男性が買ってきたものとは違うテイストのものを上映し始めたんです。積極的にそうしたセレクトを行ったのが、東京・六本木にあった俳優座シネマテン。イギリス系の美青年映画のブームになった『アナザー・カントリー』(監督:マレク・カニエフスカ)のコリン・ファース、ヒュー・グラント、ルパート・エベレットといった、当時の映画ファンには懐かしい名前が挙がります。
『ベニスに死す』(監督:ルキノ・ビスコンティ)は、美少年ビョルン・アンドレセンを明治のチョコレートのタイアップCMに起用し宣伝するも、大阪では梅田東映パラスで上映し一週間で打ち切られました。
『ベニスに死す』(監督:ルキノ・ビスコンティ)は、美少年ビョルン・アンドレセンを明治のチョコレートのタイアップCMに起用し宣伝するも、大阪では梅田東映パラスで上映し一週間で打ち切られました。
 岸野さん:それを改めてビスコンティの映画として再度公開したのも俳優座シネマテン。女性にウケる視点に変えて、新たなお客さんを呼び込む売り方をしたんですね。それでヨーロッパ映画も公開が格段に増えたんです。
岸野さん:それを改めてビスコンティの映画として再度公開したのも俳優座シネマテン。女性にウケる視点に変えて、新たなお客さんを呼び込む売り方をしたんですね。それでヨーロッパ映画も公開が格段に増えたんです。当時公開されたのは圧倒的にハリウッド映画が多くて、あとはせいぜいフランス映画だったんですけど、いわゆるニッチ、隙間的な部分を考えながらやる仕事に女性がうまくフィットしたっていうか。結局は大きな仕事よりも、そういうしんどい細かい仕事を女性がやらされて来たとも言えますが、そういう所で生きて来ました。
現在は関西でもミニシアターはほとんど支配人は女性ですよね。元々こういう職業がありますって就いた訳ではなくて、自分らで作ってるようなところがありますね。
その後約30年間の日本社会の変遷について千葉さんが言及します。
 千葉さん:1986年男女雇用機会均等法が施行になりましたが、私はその前に某国立大学文学部を出てるんです。就職活動の時、一般企業の求人票は2枚しかなくて、後は公務員か教師。または花嫁になるか、でした。
千葉さん:1986年男女雇用機会均等法が施行になりましたが、私はその前に某国立大学文学部を出てるんです。就職活動の時、一般企業の求人票は2枚しかなくて、後は公務員か教師。または花嫁になるか、でした。就職して3年後に男女機会均等法が施行されたので、お給料も上がりましたね。女性も就職してたくさん稼ぐようになったから、デートで男の子に奢ってもらわなくても、映画に行ったり飲みに行ったりできるようになってきましたから、ミニシアター増加には、そういう社会の動きも背景にあるのかな、なんて思いますね。

“苦労は忘れて楽しむ” 松井さん流映画宣伝術
宣伝に当たって苦労した思い出を伺うと、
 松井さん:思い出の苦労話はほとんどないです。性格がいいから全部忘れるんです(笑)。人生も一緒で苦労は全部忘れるから。そういう意味ではないですね(笑)
松井さん:思い出の苦労話はほとんどないです。性格がいいから全部忘れるんです(笑)。人生も一緒で苦労は全部忘れるから。そういう意味ではないですね(笑)最近印象に残った作品は?
 松井さん:やっぱり『人生フルーツ』ですね。私、この夫婦の生き方が好きなんです。私が好きということは、たぶん何人か好きな人はいると思ったから。おもしろかったのは『ヤクザと憲法』の時ですね。東京は1月2日からポレポレ東中野で公開だったんです。支配人に、この映画1月2日からやるんですか!?って聞いたら、『寛子さん、正月はヤクザ映画でしょ』って。納得!(笑)
松井さん:やっぱり『人生フルーツ』ですね。私、この夫婦の生き方が好きなんです。私が好きということは、たぶん何人か好きな人はいると思ったから。おもしろかったのは『ヤクザと憲法』の時ですね。東京は1月2日からポレポレ東中野で公開だったんです。支配人に、この映画1月2日からやるんですか!?って聞いたら、『寛子さん、正月はヤクザ映画でしょ』って。納得!(笑)同映画は東京で大ヒットとなりましたが、大阪公開にあたり、事務的な手続きだけでなく、大阪府警への対策を考えた松井さん。
 松井さん:先に名古屋と福岡と全部ヒットしたから大阪府警も何も言われへんようになったんです。これも作戦ですね(笑)。『靖国 YASUKUNI』(監督:李纓)では、直接宣伝には関わらなかったものの、第七藝術劇場とのつながりがあるためTVカメラを呼んで反対派をけん制。東京と違って大きな騒ぎには至りませんでした。
松井さん:先に名古屋と福岡と全部ヒットしたから大阪府警も何も言われへんようになったんです。これも作戦ですね(笑)。『靖国 YASUKUNI』(監督:李纓)では、直接宣伝には関わらなかったものの、第七藝術劇場とのつながりがあるためTVカメラを呼んで反対派をけん制。東京と違って大きな騒ぎには至りませんでした。『ザ・コーヴ』(監督:ルイ・シホヨス) の時もTVカメラが来てくれはったんですが、反対派の妨害もなくカメラが帰るぐらいで。そういったことは時々あるんですけど、それはそれで結構楽しいですね。私の中では(笑)

映画は国境を越えるか?岸野さんの挑戦
岸野さんの苦労の思い出は、2016年に配給を引き受けられた映画『でんげい わたしたちの青春』(監督:チョン・ソンホ)。建国高校の伝統芸術部が、文化のインターハイと言われている全国高等学校総合文化祭に出場する姿を追った映画ドキュメンタリーです。
大阪アジアン映画祭で作品を観て、監督さんと会った際に「とても良い映画ですね。日本公開できるといいですね」って伝えたところ、後日配給して欲しいという話が来たといいます。配給のお金は要らないから、日本語字幕をやり直して、宣伝のためにポスターやチラシや作ったりする初期費用は出して欲しい。回収出来て利益が出たら折半しましょう、と言う条件でした。
大阪アジアン映画祭で作品を観て、監督さんと会った際に「とても良い映画ですね。日本公開できるといいですね」って伝えたところ、後日配給して欲しいという話が来たといいます。配給のお金は要らないから、日本語字幕をやり直して、宣伝のためにポスターやチラシや作ったりする初期費用は出して欲しい。回収出来て利益が出たら折半しましょう、と言う条件でした。
 岸野さん:そこまで言われたらやらない訳には!ということでお引き受けしました(笑)。やってみるとすごく厳しかったんですよね。その理由のひとつに、日本における在日コリアンのさまざまな複雑さを私が認識していなかったのが大きいです。
岸野さん:そこまで言われたらやらない訳には!ということでお引き受けしました(笑)。やってみるとすごく厳しかったんですよね。その理由のひとつに、日本における在日コリアンのさまざまな複雑さを私が認識していなかったのが大きいです。作品自体はドキュメンタリーですけど、いわゆる王道の青春映画で、一つの大会に向けてみんながんばるっていう。メジャー作品の『チア☆ダン』(監督:河合勇人)とか『スイングガールズ』(監督:矢口史靖)なんかと変わらない映画なんです。
観てもらえたら、絶対好きになってくれる自信はあるし、もう一つはそういう南北の壁を一つでも乗り越えて欲しいなって思いもあって。やはりみんなに見せる意義はある映画の方に肩入れしてしまいますね(笑)
松井さん、岸野さんの映画に対する熱い思いと、関西の映画宣伝事情を駆け足で振り返ったシネマトーク。スマホやPCで簡単に映画が観られるようになった今日、映画はもう特別な“体験”足り得ないのでしょうか?
そんなことはありません。スクリーンを前に体験した感想を劇場で直接制作者と話したり、松井さんの「風まかせ」のような場や、このシネマトークのような出会いの場で、観客同士が顔を合わせて語り合うことで、その体験は何倍にも広がっていきます。みなさんもとっておきの映画体験を求めて映画館に出かけてはいかがでしょうか。
そんなことはありません。スクリーンを前に体験した感想を劇場で直接制作者と話したり、松井さんの「風まかせ」のような場や、このシネマトークのような出会いの場で、観客同士が顔を合わせて語り合うことで、その体験は何倍にも広がっていきます。みなさんもとっておきの映画体験を求めて映画館に出かけてはいかがでしょうか。


ゲストプロフィール

松井 寛子さん
洋邦画、劇映画、中でもドキュメンタリー映画の宣伝は、土本典昭監督、小川紳助監督はじめ、原一男監督の「ゆきゆきて神軍」など数多い。最近では「人生フルーツ」「おクジラさま ふたつの正義の物語」。ほとんどのドキュメンタリー映画監督の劇場公開された一作目から宣伝に携わる。また、居酒屋を友人と共同経営している。MC

岸野令子
映画パブリシスト/有限会社キノ・キネマ代表。主にミニシアター向け映画の宣伝・配給担当。 FB: reiko.kishino

千葉 潮
合同会社メディアイランド代表。女性と子ども応援を理念に、教育、教材、一般書の発行、編集サービスを行なう。http://www.mediaisland.co.jp/レポーター

松田洋子
(デューイ松田)
小学4年生の頃、叔母に連れられて『ゾンビ』『オーメン2』の2本立てを観たことからジャンル映画に魅せられる。アニメーター、イラストレーターを経て、2009年より「デューイ松田」名義で映画関係のフリーライターとして活動。ゆうばり国際ファンタスティック映画祭、プチョン国際ファンタスティック映画祭、CO2の取材記事や大阪アジアン映画祭の記録撮影など。(デューイ松田)
■シネマカフェ 記事一覧
-
2018年1月は大阪アジアン映画祭広報担当、音居あやさんをお迎えしました
-
2017年11月は映画宣伝プロデューサーの松井寛子さんをゲストにお迎えしました
-
2017年9月は大阪・ミナミにあるミニシアター「シネマート心斎橋」支配人、横田陽子さんをゲストにお迎えしました
-
2017年7月は神戸・元町商店街にあるミニシアター「元町映画館」支配人、林 未来さんをお招きしました
-
2017年5月は大阪九条のミニシアター「シネ・ヌーヴォ」支配人、山崎紀子さんをゲストにお迎えしました