昨日の世界(シュテファン・ツヴァイク)
 |
|
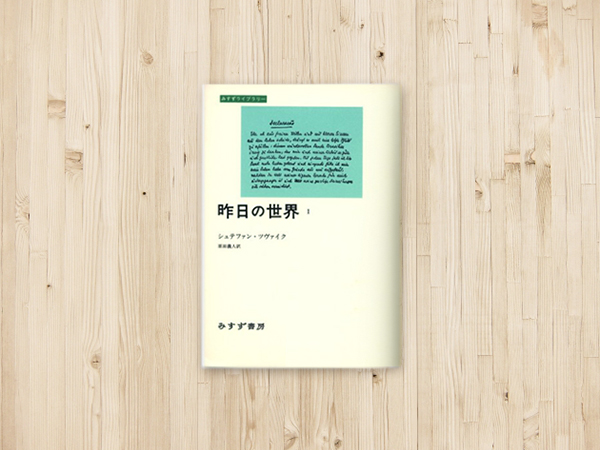 今日の世界から見ても再評価すべき点がある 昨日の世界
シュテファン・ツヴァイク 前回のおすすめの一冊、町山智浩さんの『映画と本の意外な関係!』にも紹介されている映画「グランド・ブダペスト・ホテル」(ウェス・アンダーソン監督 2013年)は、セットや衣装や色彩、撮り方がとてもオシャレ。中欧の歴史をうまく盛り込んだ、とても面白いミステリー・コメディです。映画の最後に、「シュテファン・ツヴァイクの作品にインスパイア(触発)された」という文言が大きく現れます。そのツヴァイクの作品のなかでも最高傑作とされる回想録『昨日の世界』が今月のおすすめの一冊です。
『昨日の世界』は、副題「一ヨーロッパ人の回想」が示すように、「ヨーロッパ人」として生きようとしたツヴァイクから見た同時代史です。ツヴァイク(1881-1942)は、ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれました。20歳で詩人としてデビューし、戯曲、伝記、小説、評論など多くの作品を発表し、ベストセラー作家として富と名声を得ました。その作品は世界中で翻訳され、当時もっとも親しまれた作家のひとりでした。代表作の『マリー・アントワネット』『ジョゼフ・フーシェ』は日本でも文庫化されています。全集もみすず書房から刊行されています。 ツヴァイクは、彼の父親たちの世代が繁栄を享受した時代のウィーンを「安定の世界」と呼びました。すなわちオーストリア=ハンガリー帝国の末期にあたるフランツ=ヨーゼフ皇帝の時代、ウィーンには劇場文化、カフェ文化が咲き誇ります。ウィーン市民は、「共存共栄」を重んじて、「時には愚弄し合うことはあっても平和に共同の生活」を送っていました。ユダヤ人にも市民としての権利が認められ、経済的な成功を収めたユダヤ人ブルジョワたちの子世代は、芸術、文学、学問の世界で名を成すことに邁進できたのです。 この頃はまた、ヨーロッパを「旅券や許可証なしに旅行することができた」時代でした。そうした時代に青春を過ごしたツヴァイクは、「コスモポリタン(世界市民)」な「ヨーロッパ人」というアイデンティティをもつようになったのです。 しかしその後、民族や国家という意識が強まり、個人の自由や権利が制限される時代になっていきます。異国や異民族を憎み、罵倒する世界になったことをツヴァイクは嘆きます。それでも第一次大戦の頃は、「言葉がまだ力を持」ち、「「宣伝」という組織化された虚偽によって死滅する」には至っていませんでした。指導者たちは「野蛮人」「軍国主義」とみなされることを嫌い、「文化宣伝に努めた」といいます。 ところが、1930年代、さらに国際情勢は緊迫し、ユダヤ人で平和主義者のツヴァイクの本は焚書になります。34年、家宅捜索を受けたツヴァイクは、愛する故郷オーストリアを離れ、ロンドンに亡命します。38年、ナチスドイツによるオーストリア併合によって、ツヴァイクは無国籍者となります。故郷と蔵書や蒐集したすべてのものを失い、母語での出版の途を絶たれ、大きな喪失感を味わったツヴァイクは、ニューヨーク、そしてブラジルへと渡り、42年に妻と服毒自殺します。60歳でした。 ツヴァイクは戦争への関与や戦意発揚への加担を嫌い、戦時中に平和を唱える論文や戯曲を発表するなど、平和主義者、ヒューマニストであり続けました。しかし、どの党派にも属さず、「政治性を持たない」ことを徹底したツヴァイクの「個人主義」に対しては、同時代人や後世の批評家からの批判もあります。戦後、ツヴァイクの作品が発表当時ほど読まれなくなったのも、焚書によってドイツ語圏から消失したことに加えて、その「前時代的」な古くさい「個人主義」は克服されるべきとみなされたからだと言われます。 しかし、ツヴァイクの思想と、彼が書き残した『昨日の世界』には、今日の世界から見ても再評価すべき点があるように思います。ツヴァイクを再評価しているのはアンダーソン監督だけではないようで、アメリカでは2000年代に入って、ツヴァイク作品の復刊が相次ぎ、新聞雑誌で取り上げられることも増えているそうです。「グランド・ブダペスト・ホテル」効果もあって、ロケ地となったドイツやチェコの町も脚光を浴びているようです。 参考: 佐久間文子「ツヴァイク復活?」『出版ニュース』2015年1月号 マット・ゾラー・サイツ『ウェス・アンダーソンの世界 グランド・ブダペスト・ホテル』(DU BOOKS 2017年) 昨日の世界
シュテファン・ツヴァイク (著) みすず書房 ナチズムが席巻するヨーロッパを逃れて、アメリカ大陸に亡命したツヴァイクは、1940年ごろ、第二次世界大戦勃発を目にして、絶望的な思いで、本書を書き上げた。ウィーンの少年時代から書き起こされたこの自伝は、伝統の織り成すヨーロッパ文化の終焉を告げるものであり、著者が一体化した一つの時代の証言であり、遺書である。 出典:amazon  橋本 信子
同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











