弱いつながり―検索ワードを探す旅(東浩紀)
 |
|
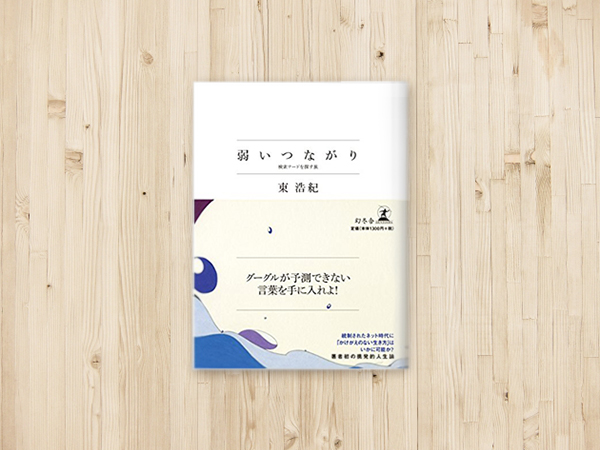 場所を変えることで新しい「検索ワード」が見えてくる 弱いつながり
検索ワードを探す旅 東浩紀(著) 著者の東浩紀さんは批評家、思想家として活躍されています。最近ではチェルノブイリ原発へのダークツーリズムを企画したり、福島第一原発の観光地化を提唱したりしていることでも注目されています。
本書は、東さんが旅先で見たこと考えたことをもとに読みやすい文体で書かれているので、旅のエッセイとして読むこともできます。 「弱いつながり」という言葉は、社会学や経営学でよく使われる「弱い絆」という概念と近い考え方です。 転職者の満足度に関するある社会調査によると、就職先の紹介者は、ごく近しい人の場合よりもちょっとした知り合いのときのほうが、転職を果たした人に高い満足度が見られるという結果が導かれました。 こうした結果になるのは、「強い絆」で結ばれた人どうしは同じ世界の人であるため予測可能な転職先しか紹介してくれないが、「弱い絆」で結ばれた人は思いがけない未知の世界に誘ってくれる可能性が高いからだと言われています。 そこで東さんは、人生の充実のためには、強い絆と弱い絆の双方が必要だと説きます。もちろんそれは就職の世話というような人間関係に限定した話ではありません。多様な世界と弱いつながりを持つことが私たちの視野を広げ、人生を豊かにしてくれるということです。 では弱いつながりはどうすれば得られるのでしょうか。 現代は、インターネットがそれを実現してくれそうです。私たちはインターネットによって、大量の情報に触れることができ、また遠方の景色を見ることも、そこに住む人々と通信することもできます。まさに広い世界とつながったように感じます。 しかしその世界は、実は検索エンジンの上位に並ぶ限られた選択肢のなかにとどまっており、既存の人間関係を固定化し、未知の世界につながり飛躍する機会をむしろ奪ってしまうと東さんは指摘します。なぜなら私たちは、知らないこと、見えていないことを検索ワードにすることができないからです。 そこで本書では、私たちが未知の世界を知るためには、環境を意図的に変えること、普段と違う場所に身を置くことが大切だと繰り返し説かれています。 東さんは、20年ほど前にポーランドのアウシュビッツ強制収容所跡を訪問しました。ご本人いわく、単なる観光客として、「表層を撫でた」だけ。それでも現地に行って、異様な空気を感じ、残されたモノを自分の目で見たことは、のちの仕事に大きな影響を与えたといいます。 「観光」でいいのです。表面的でもいいのです。文字通り場所を変えることで、新しい「検索ワード」が見えてくるのだと東さんはいいます。 最近、本書を再読したところ、かつてよりも実感をともなって、強い共感をもって読むことができました。それは私が、本書や古市憲寿氏の『誰も戦争を教えられない』に後押しされ、久しぶりにヨーロッパに行ってダークツーリズムの旅をし、現地に行く意義や効果を再確認してきたからだと思います。 「観光客」として違う場所を訪れ、「新しい欲望」―物欲ではなく新しいことを知りたいと思う欲望―を得ることによって、私たちの人生には別の道や世界が開かれる。とても前向きで楽しくて心強い提言ではありませんか。  橋本 信子
同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











