下り坂をそろそろと下る(平田オリザ)
 |
|
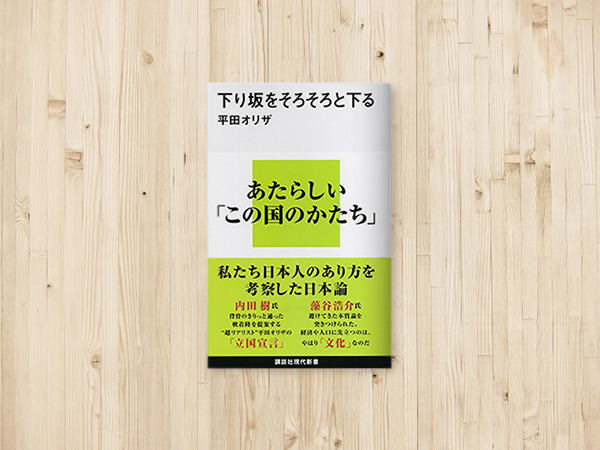 問題解決能力よりも、問題を発見できる能力 下り坂をそろそろと下る
平田オリザ(著) 私たちは下り坂の途中にいます。日本はすでにアジア唯一の先進国ではありません。この先、人がどんどん増えて経済が右肩上がりに拡大していくことは望めません。日本各地で人が出て行ってしまう、新しい人が増えないという焦りが募っています。ところが、その対策はいまだに工場誘致であったり、住宅建設であったりします。
しかし、地方から若い世代が出て行ってしまうのは、雇用が少ないからだけではありません。つまらないから、文化的な刺激がないから、偶然の出会いがないからというのが決定的なのです。それなら、つまらなくないまち、自己肯定感を引き出すようなまち、ハイセンスなまちづくりに注力すべきであると、本書の著者、平田オリザさんは提言します。 オリザさんは、世界で活躍する劇作家、演出家、教育者です。全国津々浦々で演劇を取り入れたワークショップを行い、コミュニケーション能力の向上、異文化理解、異文化交流、地域活性化を支援しています。その経験や手腕を買われて、いくつもの大学の新学科創設や入試改革にも携わっておられます。 多くの職業がAIに取って代わられていくという時代には、問題解決能力よりも、問題を発見できる能力こそが必要になってくるとオリザさんは指摘します。そして問題を発見するためには、幅広い視野と、他人の状況に思いをはせる力が必要だといいます。 そういった力を養うには、小さいころから本物を見たり触れたり体験したりすること、それによって身体感覚(例えば味覚やセンスなど)を養うことが必要です。 しかし、首都圏と大都市圏、地方都市と都市でない地域では、そうした「文化資本」に触れる機会が、何倍どころか百倍くらい違います。さらに、「文化資本」は、家庭の経済状況や、親の文化的な習慣にも大きく左右されます。地域格差と経済格差が掛け合わされると圧倒的な差ができてしまいます。 では地方には救いがないのかというとそんなことはありません。本書でオリザさんが紹介している自治体や大学などは、いずれもかなりハンデがある地方にありますが、新しい文化の拠点、新しい試みが成功しているところとして国内外から注目を集めています。 なかでも私が特に興味を持ったのは、兵庫県豊岡市の城崎国際アートセンターの取り組みです。コウノトリの郷としても注目を集めている豊岡には、稼働率が著しく低い会議場がありました。豊岡市は、この施設を、公募で選ばれたアーティストにゆっくり滞在してもらい、舞台芸術作品を制作してもらうアートセンターにリニューアルしたのです。国内外から大きな反響があり、年間稼働率は90%を超えているそうです。 アーティストには成果発表会やワークショップなど地域還元事業も行ってもらいます。それによって、城崎の子どもたちは地元で世界トップレベルの芸術に触れる機会を得ます。高いお金をかけて一回限りの公演を招聘しなくとも、向こうからやってきて、城崎初の作品を生み出してくれるのです。 下り坂の途中にいることを認めることは寂しさを伴います。それでも、その寂しさに向き合いながら、ここでよいのだ、ここがよいのだと思えるまちや社会や国をつくっていきたいものです。 下り坂をそろそろと下る
平田 オリザ (著) 講談社 「これからの日本」をどうするか? 人口減少、待機児童、地方創生、大学入試改革…。日本が直面する重大問題の「本質」に迫り、 あらためて日本人のあり方について論考した快著! 出典:amazon  橋本 信子
同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











