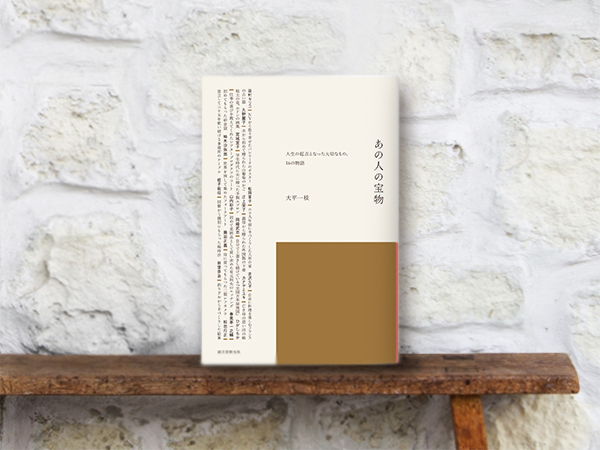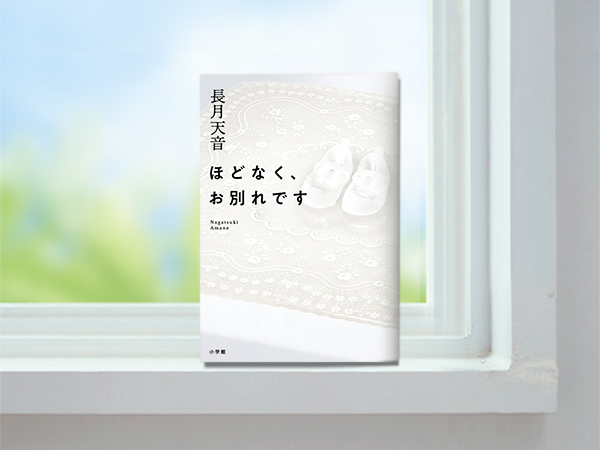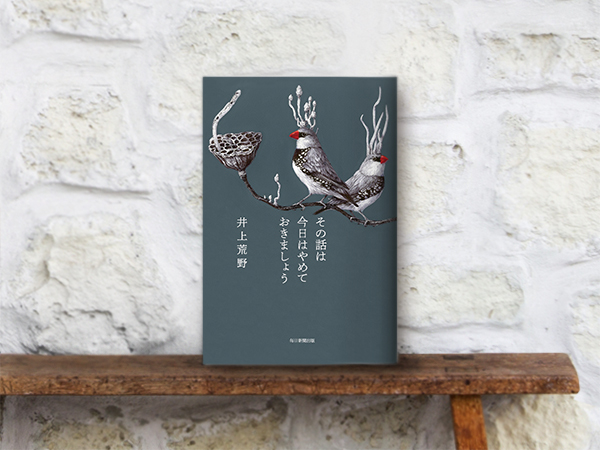4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した
 |
|
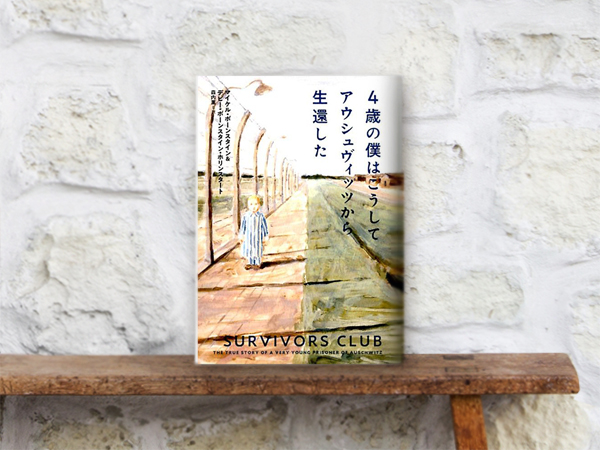 胸を打つ良質なノンフィクション 4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した
マイケル・ボーンスタイン(著) 毎週日曜に、『関西ウーマン」に連載していただいている「千波留の本棚」。コツコツ続けているうちに、連載200回を超えました。継続は力なりで、細々と続けるうちに色々な方に読んでいただけるようになりました。
そしてこのたび、NHK出版様から「千波留の本棚」あてに、マイケル・ボーンスタインさんの『4歳の僕はこうしてアウシュビッツから生還した』という素晴らしい本をご献本いただきました。ありがとうございます! マイケルさんの左前腕には「B-1148」という刺青があります。それはアウシュビッツに入れられた日に彫られたもの。その時マイケルさんはまだたったの4歳でした。 アウシュビッツに送り込まれたユダヤ人の中でも、多くの子供や老人は「労働に適さない」と判断され、早めに命を奪われたそうですが、マイケルさんは無事に生還しました。 しかし、ご自身の体験を執筆したり、自分から人前で話すことはしなかったそうです。 その理由は、容易に喋ることができないほど つらい体験だったことと、間違ったことを口にしたくなかったから。 幼かったマイケルさんの記憶は、ある部分は鮮明だけど、ある部分はぼやけてしまっていて、全てを正しく語る自信が持てなかったのだそう。 しかしある時偶然、解放後のアウシュビッツでソ連兵が撮影した、ユダヤ人の子どもたちの写真の中に、自分がいるのを発見します。 マイケルさんがその写真を見たのは、ホロコーストの噂はデマで、本当はそんなに酷い場所ではなかったと主張するウェブサイトだったのです。 解放されたばかりの子どもたちが「健康そうに見える」から、と。 マイケルさんは衝撃を受けました。 そして自分はあの悲惨な体験を語らねばならないと決意します。 戦後70年以上経っていましたが、テレビプロデューサーの娘さんの力を借り、取材、執筆に取り組んだのでした。 若い世代に読んでもらいたいと、ドキュメンタリーというよりは小説風に書かれていて、とても読みやすいです。 しかし、これまで読んだアウシュビッツ関連の小説に比べると、非常に抑制が効いています。 むしろ声高に悲惨さを語るのではなく、あえて淡々と述べるように心がけたのではないかと感じました。 それは、なるべく事実を捻じ曲げないよう、あったことをそのまま伝えなければという使命感だと思います。 1940年、ドイツ占領下のポーランドに住んでいたマイケルさん。ユダヤ人に関する悲惨な噂を聞いても、なかなか本当のこととは思えないし、住み慣れた場所を離れたくはない……。 様々な理由から、そこにとどまったユダヤ人たちがどんどん恐ろしい事態に巻き込まれていく様子や、なんとか活路を見出そうとするマイケルさんのお父さんたちの姿に、のちの歴史を知っている私は、息が詰まりそうでした。 同じ人間であり、家に帰ればいいパパかもしれないドイツ人が、なぜあんなにも残酷なことができたのでしょうか。 結局マイケルさんの親戚は、亡命する、地下(隠れ家)に潜る、そのままとどまるの三つに別れることになります。 マイケルさんの家族は「そこにとどまった」ため、最終的にアウシュビッツに行くことになったわけです。 4歳の「僕」がアウシュビッツから生還できた理由は、さまざまな偶然の積み重ねで、とても説明しきれるものではありません。ぜひご自身で読んでみてください。 最後に、私がこのドキュメンタリーの中でもっとも胸痛めたのは「おばあちゃん」との別れでした。 余談ですが、マイケルさんの親戚の何人かは、杉原千畝にビザをもらって生き延び、のちに奇跡的に再会することができました。 このノンフィクションの中に「杉原千畝」という文字を見出した時、本当に嬉しく、誇らしかったです。 4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した
マイケル・ボーンスタイン(著) NHK出版 1940年にドイツ占領下のポーランドに生まれたマイケルは、ゲットーや収容所暮らしを余儀なくされたのち、わずか4歳でアウシュヴィッツに送られた。なぜ、子どもが次々に殺されていった収容所で、彼は6か月も生き延びられたのか?悪や絶望がうずまく世界の中で、ひたむきに前を向いて生きたマイケル一族の姿が胸を打つとともに、家族の絆や、希望を失わずに生きることの大切さをあらためて教えてくれる良質なノンフィクション。 出典:楽天  池田 千波留
パーソナリティ・ライター コミュニティエフエムのパーソナリティ、司会、ナレーション、アナウンス、 そしてライターとさまざまな形でいろいろな情報を発信しています。 BROG:「茶々吉24時ー着物と歌劇とわんにゃんとー」 ヒトが好き、まちが好き、生きていることが好き。だからすべてが詰まった本の世界はもっと好き。私の視点で好き勝手なことを書いていますが、ベースにあるのは本を愛する気持ち。 この気持ちが同じく本好きの心に触れて共振しますように。⇒販売HP/Amazon |
OtherBook