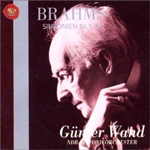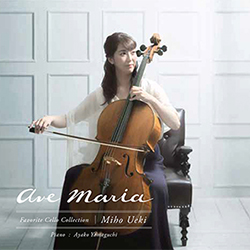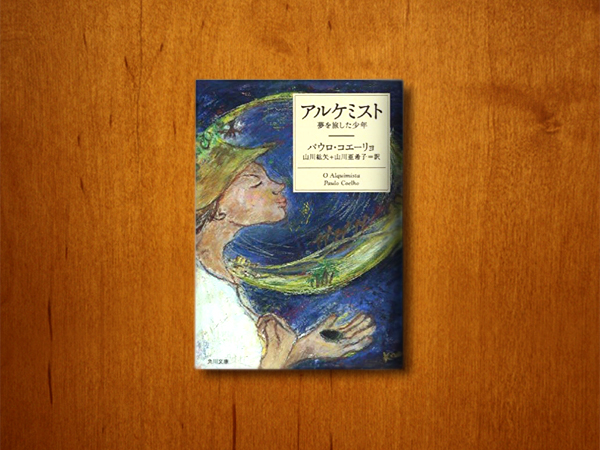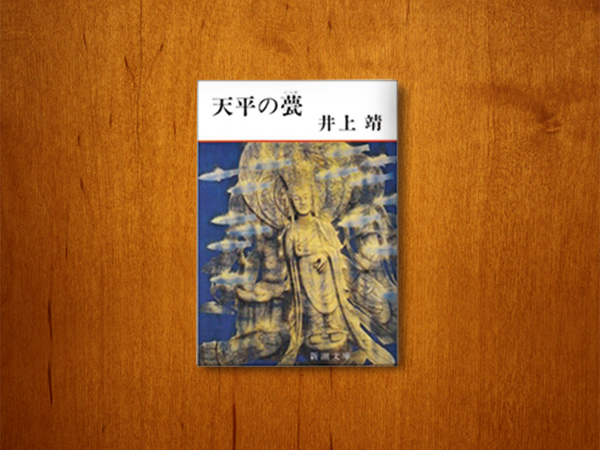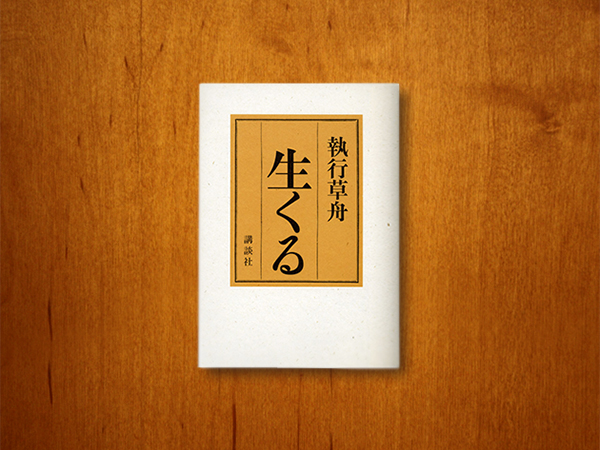本心(清水雅洋)
 |
|
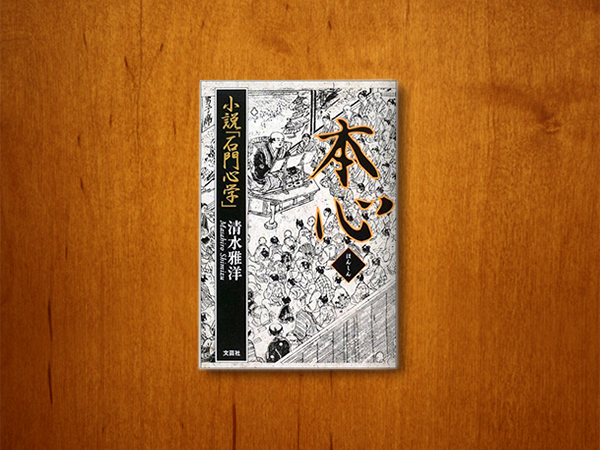 本性とは何なのか? 本心
清水 雅洋(著) 石田梅岩(ばいがん)という名前を聞いたのは何年前でしたか…。
商いの道を説いた、とあったのですが、 それを「商道」と表していたことが印象に残っています。 武士道と同じように、商人にも商道と言われるものがあるんだな、 と初めて知りました。 梅岩の思想、石門心学(せきもんしんがく)は、難しいのかな…?と思っていましたが、 そんなことはなく、むしろ町民のために道徳を説いたので、 説話の例えも面白く、なじみやすいものばかり。 その上、江戸時代に広がった石門心学は、日本人の心の根幹に根付き、 私たちの軸となっていたことに、心底驚きました。 まずは、梅岩の生い立ちからお話ししましょう。 1685年、京都の亀岡にて、農家の次男として生まれます。 梅岩という名前が付けられるまでは、勘平(かんぺい)と呼ばれていました。 幼い頃から学問が好きで、寺子屋の先生にも褒められる利発な子どもでした。 ある日、山で拾った栗を持ち帰った勘平は父親にひどく叱られます。 (本文より) 「お前、その栗、どこで拾うてきた」 「どこって、わしの家の山に落ちていたんじゃ」 「うちとこの山か、ほんまじゃな。隣の山との境じゃなかったんやろな。 きっとやな」 「そりゃあ、そう言われりゃあ、隣の山との境あたりやったけんど、 でもいいやろう、そんなこと」 「よくない。うちとこの山の栗はまだそんなに熟しきっとらん。その栗は隣の山に生えておった木の枝からうちの土地に落ちてきたものに違いない。勘平、お前人様のものを拾うてきたんじゃ。すぐ返してこい。いいか、落ちていたところに間違いないよう、きっちり置いてくるんじゃぞ」 勘平のあどけない顔はみるみる崩れ、双の眼から大粒の涙がこぼれてきた。 このことが、梅岩の道徳心の根本形成に大きな影響を与えます。
11歳で京都の商家に丁稚(でっち)に出されますが、4年後に倒産。 再度、新しい丁稚先へ行くことになります。 どこへ出されても、まじめで誠実。人の嫌がる仕事を率先して行う姿に、皆から一目置かれ、人望を得るようになります。 丁稚をしながらも、いつか人の師表になりたいと夢を持ちますが、 その道は前途多難です。 ある日、遅くまで勉学に励む梅岩(勘平)を見て、仲間の丁稚が尋ねます。 (本文より) 「わても本好きやけど、到底勘平どんの読書量にはおっつかへん。 勘平どんはなんでそんなに本を読むんや」 「そういうあんたも相当の読書家やが、なぜそんなに本を読むんや。 まず、それからうかがおう」 「決まっているやろ。 物知りになっていずれお店(たな)を退いたら学塾を開くつもりやがな。 わては物知り人になって金儲けするのが夢なんや」 「わてが本を読むのはちょっとあんたとは違うなあ」 「どう違うんや」 「わてが本を読むのは古聖賢の心を知り、 人々の手本になるような人間になるためや」 仲間の丁稚は驚いた。 こんな途方もないことを考えている人間がこの世にいようとは… 大きな目標に向かって努力を続けますが、 同年輩の丁稚仲間が次々と手代になり、完全に水をあけられ、焦りが募ります。
実社会でもうまくいかず、勉強も進まない…。 (本文より) 「ああ、わしは遅れを取った。わしの開塾思案など夢のまた夢じゃあ。 何が人の手本じゃ。笑わせらあ。やっぱり二度目の奉公は失敗じゃった。 わしゃあ、ただのアカンタレや」 人間とは何か、何を目標にして生きているのか、 生きる意味とは…?
30歳に手が届こうとする勘平は、答えが見つからず、もがき苦しみます。 人はそれぞれの性(本性)に従って生きるべきだ。 しかし、その本性とは何なのか? 梅岩が生きた江戸時代中期は、戦ばかりの非生産的な社会から、 平和で安定した社会へと変換する高度成長期でした。 そんな中、私腹を肥やし不正する商人に道徳を説く必要があったのです。 商家で丁稚をしていた梅岩は、 道徳や哲学の必要性を誰よりも肌で感じていたのかもしれません。 思想の生まれた背景には当時の社会情勢が深く関係していたのではないかと思います。 35歳の時、小栗了雲(りょううん)という先生に出会います。 その師の下で修業を重ねた末、6年経って遂に悟達、つまり悟りに至るのです。 なんとそのきっかけは、郷里の母が病気になり、 心配するあまり自分の懐疑の念を忘れたことでした。 「我なし」の境地に至ったのです。 その後も自分の中にある欲を捨て「無」になるため、さらに厳しい修業を重ねます。 ただ単に博識になりたい、という個人的な欲ではなく、 どうすれば世の中が良くなるのか、 そのために自分の人生を捧げた姿が浮かんできました。 そして、粘り強く向き合う姿勢から強い信念が伝わります。 人間の根本、本性を知らねば…。と、丁稚をしながら身を粉にして努力した梅岩。 そこに生命の燃焼があり、最後までやりきる姿に心動かされました。 「なかなか結果が出ない」 自分に置き換えると、これまでの音楽人生、うまくいかないことの連続でした。 挫折しそうになって恩師に相談したとき、その話の中で 「先生は自分よりもっと多くの挫折を知っている」と、直感的に思いました。 すると、なんだか自分の悩みがちっぽけに思えてきた。そんなことがありました。 梅岩は45歳にして私塾を開設。初めは誰にも相手にされませんでしたが、 少しずつ門下生が増え、60歳で亡くなった後は弟子が後を継ぎ、 その組織は全国に広がりました。 さて、そんな梅岩に重なる音楽があります。 ドイツを代表する作曲家の一人、ブラームス(1833-1897)の交響曲第一番です。 ブラームスの音楽はいぶし銀のような渋さがあります。聴けば聴くほど良さが分かる、そんな音楽なのです。 ベートーヴェンやモーツァルトの功績を引き継いだブラームスですが、 交響曲という、作曲家にとっては特別なジャンルを手掛けるに当たり、 なんと約20年もの歳月を費やしました。 交響曲第一番の冒頭、ティンパニーが「ドン、ドン、ドン、ドン…」とゆっくりしたテンポを刻みます。まるで、20年の苦悩の幕開けのような悲劇的な響きです。 これを聴くとブラームスのように、梅岩のように、 何があっても前に向かっていこうと、そんな気持ちになります。 さて、タイトルの「本心」ですが、 これは梅岩の死後、思想の元となる人間の性について、 もっと分かりやすい表現はないかと思案した弟子が、 心の源ということをたどり、そこからひらめいた言葉です。 自分にできることは本当にちっぽけですが、 偉人の背中を見て、励まされながら前に進んでいきたいと思います。 本心
清水 雅洋(著) (著) 文芸社 (2003) 日本資本主義の精神となった思想は一体何か? プロテスタンティズムをもしのぐ強烈な思想が存在したのだ! 日本を経済大国たらしめた精神を探求した大河小説。 出典:amazon  植木 美帆
チェリスト 兵庫県出身。チェリスト。大阪音楽大学音楽学部卒業。同大学教育助手を経てドイツ、ミュンヘンに留学。帰国後は演奏活動と共に、大阪音楽大学音楽院の講師として後進の指導にあたっている。「クラシックをより身近に!」との思いより、自らの言葉で語りかけるコンサートは多くの反響を呼んでいる。 Ave Maria
Favorite Cello Collection チェリスト植木美帆のファーストアルバム。 クラッシックの名曲からジャズのスタンダードナンバーまで全10曲を収録。 深く響くチェロの音色がひとつの物語を紡ぎ出す。 これまでにないジャンルの枠を超えた魅力あふれる1枚。 ⇒Amazon HP:http://www.mihoueki.com BLOG:http://ameblo.jp/uekimiho/ ⇒PROページ ⇒関西ウーマンインタビュー記事 |
OtherBook