太陽の子(灰谷健次郎)
 |
|
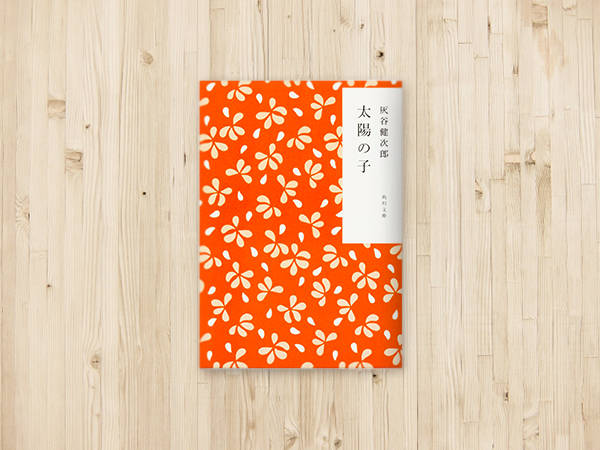 知らなくてはならないことを、知らないで過ごしてしまわない 太陽の子
灰谷健次郎(著) 子どもの頃、理論社の「大長編シリーズ」を愛読していました。私にとっては特別な、原点のような作品群でした。そのうちの一冊である『太陽の子』を最近になって文庫で読み直しました。何十年ぶりかの灰谷作品は、子どもの頃以上に衝撃的でした。
『太陽の子』は、1970年代中頃の神戸の下町が舞台です。琉球料理店「てだのふあ・おきなわ亭」のひとり娘ふうちゃんは、常連さんたちに可愛がられ、明るく聡明に、のびのびと育ちました。「てだのふあ」とは、沖縄のことばで「太陽の子」という意味です。沖縄出身の両親が、生まれてくる子が元気で明るい子になるようにと店の名につけました。 幸せいっぱいのふうちゃんでしたが、6年生になったころから、大好きなおとうさんが心の病になってしまいます。故郷の沖縄・八重山のことをいっぱい話してくれていたおとうさんがほとんど口をきかなくなり、不可解な行動をとるようになります。 やがてふうちゃんは、おとうさんの心の病には沖縄での戦争が関係しているのではないかと思うようになります。担任の先生や、お店の常連で沖縄出身のお兄さんに協力してもらい、沖縄のことを深く理解しようとします。そうしていくなかで、おとうさんの親友のおじさんが片腕になったわけや、常連のお兄さんが行く末を心配して世話しようとお店に連れてきた沖縄出身の少年とその家族の壮絶な過去を知っていきます。 ありったけの地獄を集めたともいわれる沖縄戦、戦後のアメリカ軍による土地の接収や米軍兵士による暴行、本土復帰後も集団就職せざるを得なかった貧しさ、渡っていった先で受ける差別、沖縄の人々はたくさんのつらい悲しい目にあってきました。そのような沖縄の人々の優しさ、お互いを大事に思う温かさ、その深い愛情に包まれて育ったふうちゃんの清いまっすぐさに心打たれます。 「知らなくてはならないことを、知らないで過ごしてしまうような勇気のない人間に、わたしはなりたくありません」。ふうちゃんのことばです。この作品を読んだとき、沖縄の人々が抱えてきた苦しみを知っておくべきだった、せめて今からでも、その苦しみがまだ続いていることに向き合いたいと思いました。 今年は戦後80年。戦時中のことを知る人がいよいよ少なくなります。知らなくてはならないことを知っていきたいと思います。 太陽の子
灰谷健次郎(著) KADOKAWA (1998/6/23) ふうちゃんが六年生になった頃、お父さんが心の病気にかかった。お父さんの病気は、どうやら沖縄と戦争に原因があるらしい。なぜ、お父さんの心の中だけ戦争は続くのだろう? 著者渾身の長編小説! 出典:amazon  橋本 信子
大阪経済大学経営学部准教授 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











