ある町の高い煙突(新田次郎)
 |
|
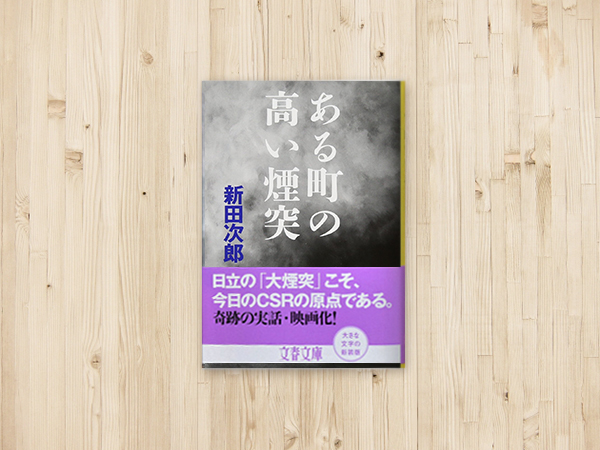 誠意と忍耐の大煙突 ある町の高い煙突
新田 次郎(著) 茨城県日立市に世界一高い煙突がありました。日立鉱山の煙害を解決するため1914(大正3)年に建てられた高さ156mの「大煙突」です。
新田次郎氏による『ある町の高い煙突』は、日露戦争後から第一次大戦開始ごろを舞台に、鉱山から出る亜硫酸ガスによる煙害に苦しむ村の人々と鉱山会社とが、互いに誠意を持って忍耐強く交渉に当たって煙害の解決を実現したという実話をもとにした小説です。 気象学者として長く気象庁に勤務してきた新田氏は、日立市立天気相談所所長の山口秀男氏にすすめられて、1969年にこの小説を書きました。「日本は世界一の公害国であり、あらゆる種類の公害が発生し、そして一つとして、完全に解決したということを聞いたことのない奇妙な国」だった頃です。 気象ともっとも関連の深い煙害に興味を持っていた新田氏は、その煙害の問題を見事に解決した実例が、すでに数十年前にあったということに強い関心を抱きました。 新田氏は、山口氏の案内で、日立市の現場を訪れ、鉱山が設置した気象観測所の記録を見せてもらい、さらに農民側代表として活躍した関右馬允(せきうまのじょう)氏を紹介されます。関氏は当時80歳でしたが、若者と山野を歩き回れるほどお元気で、貴重な記録とともに記憶も提供されたそうです。 その関氏をモデルとする本作の主人公、関根三郎は、入四間(いりしけん)村の名家の跡取りとなるべく養子に来た人です。将来は外交官になろうかという前途有望な若者でしたが、養父や村民らから、進学せずに村に残って煙害対策に取り組んでほしいと懇願されます。悩んだあげく、三郎は覚悟を決めて村に残りました。 三郎は、被害の状況をつぶさに記録し、会社に補償を求めます。会社はその都度、補償には応じますが、生産量が増えるにしたがって、被害はますますひどくなっていきます。山から排出された黄色い煙が生き物のように山を下りてきて村の作物を覆っていく様子、煙を浴びた植物が生気を失っていく様子、動物や人が健康を害していく様子などが、目の前で起こっているかのように描かれます。 会社も事態を打開すべく有害物質を薄めて低い位置から排出する方式の煙突を建造しますが、2度も続けて失敗に終わります。このままでは、村民は村を捨てて、どこか開拓地に移るしかなくなるという事態に陥ります。 三郎は、煙害そのものを発生させないようにしなくてはいけないのではないかと考え、同じ考えに至っていた鉱山の担当者、専門の学者らと解決策を探ります。そして行き着いた方法は、巨大な煙突によって煙を上空に排出し、拡散させるというものでした。 大煙突建造は巨額の費用が見込まれるうえ、当時は効果が疑わしいという声が優勢でした。しかし、鉱山の社長は社運を賭けて大煙突を建てることを決心します。そして結果は見込み通り、煙ははるか上空で大気によって薄まり、煙害は克服されたのでした。本書では、大煙突によって煙が希釈されるメカニズムが、反対意見も含めて分かりやすく述べられており、新田次郎氏の本領発揮と言ったところです。 鉱山会社は荒れた山に再び植林を進め、付近一帯、煙害に強い桜が花を咲かせるようになります。その後、煙から有害物質を除去する技術が開発され、大煙突は当初の使命を終えます。1993年、大煙突は上部が倒壊して1/3の高さになってしまいましたが、折れた箇所を修復して、現在も蒸気を排出する煙突として働いています。倒壊から30年経ちますが、煙突は今も地元の人々に愛されているようです。 なお、この小説は1969年の読書感想文コンクール高校の部の課題図書になりました。聡明で責任感あふれる主人公と外国人技師との友情や、淡いロマンスといったストーリー展開も魅力的です。2019年には映画化もされています。映画も大煙突もぜひ見ようと思います。 ある町の高い煙突
新田 次郎(著) 文藝春秋:新装版 (2018年) 初版(1969年) 茨城県日立市の象徴である「大煙突」は、いかにして誕生したか。外国人技師との出会いをきっかけに、煙害撲滅を粘り強く訴えた若者と、世界一高い煙突を建てて、住民との共存を目指した企業の決断。足尾や別子の悲劇を日立鉱山では繰り返さない―今日のCSR(企業の社会的責任)の原点を描いた力作。 出典:amazon  橋本 信子
大阪経済大学経営学部准教授 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。専門は政治学、ロシア東欧地域研究。2003年から初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発にも従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











