「国境なき医師団」になろう!(いとうせいこう)
 |
|
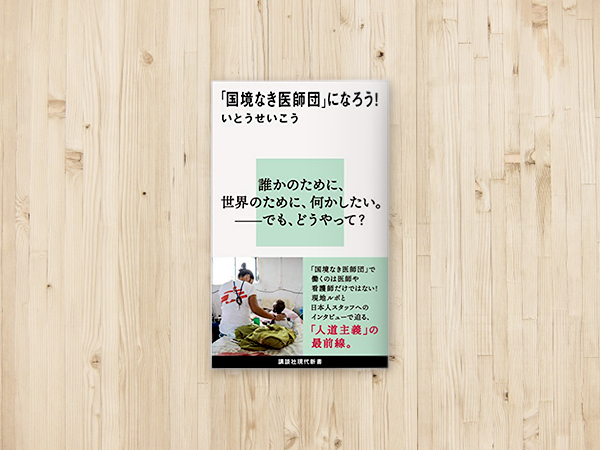 心を揺さぶられ、自分も何かしたいと思わせる一冊 「国境なき医師団」になろう!
いとうせいこう(著) 紛争地や災害地にいち早く駆け付けて医療支援をおこなう「国境なき医師団」(MSF)は、1999年にノーベル平和賞を受賞している国際NGOです。
作家・クリエイターとして広い分野で活躍されている本書の著者、いとうせいこうさんは、「些少ながら」寄付していた縁で、2015年にMSFからインタビューを受けます。この時、いとうさんからもMSFについてあれこれと尋ねたところ、知らないことだらけ、驚くことだらけであることに気づいたそうです。そこで彼は、MSFの活動を取材し広く発信する役を買って出ます。 とはいえ、MSFが活動するのは、紛争地や災害地などの危険な場所です。例えば、内戦が続く南スーダン、その南スーダンからの難民が殺到しているウガンダ、貧困と大地震の影響で疾病、ケガ、コレラの蔓延に苦しむハイチなど。 これらの地域では、取材することがMSFの活動の邪魔になりかねませんし、紛争の当事者からスパイ行為とみなされる恐れもあります。さらに、MSFの支援を受ける人たちは、戦乱や暴力などによって、体だけでなく、心も深く傷ついています。写真一枚撮るのにも、細心の注意を払う必要がありました。 本書は、そのような大変難しい条件のもとで得られた貴重な成果です。その内容は、現地の様子と、そこで働く人たち、とりわけ非医療分野で働く人びとの語りから構成されます。優しい語り口ながらも、心を揺さぶられ、自分も何かしたいと思わせる一冊です。 さて、そのMSFですが、活動の三大原則は、「独立、中立、公平」です。 MSFは、独立性を保つため、活動資金の95%を民間の寄付でまかなっています。そのうち、個人の寄付が88%を占めているとのこと。国家など公的資金からの拠出は1%強しかありません。 企業からの寄付も場合によっては断ることがあります。武器製造に関連している企業からは寄付を受けません。グループ企業や子会社に武器製造関連企業がある場合も同様です。製薬企業からも利害関係が生じないようにするため寄付を受けません。日本のMSFは、酒、煙草の製造、ギャンブルに関わる企業からも受け取っていないそうです。 中立とは、患者さんを選ばないということ。政治的に対立する勢力がある場合は、両方から患者さんを受け入れます。目の前で苦しんでいる人を助けるという「医の倫理」を貫いています。 そして、公平とは、民族、宗教、政治的信条などに関係なく、等しく医療を届けるということです。 この三原則を徹底するため、MSFは活動場所に武器を持ち込みませんし、持ち込ませません。丸腰のMSFが危険な地域で医療活動を行うためには、現地での信頼関係がなにより大事になります。現地の政府や紛争当事者らとの細かな交渉も大切な活動のひとつです。 またMSFの活動地は、戦争や紛争、災害や飢饉、疫病などの発生している地域が多いので、非医療分野のバックアップが欠かせません。 そのため、スタッフの半数は、物品調達、安全確保、環境整備、広報、交渉などを担当する非医療従事者です。彼らロジスティシャンやアドミニストレーターと呼ばれるスタッフが、医師や看護師、助産師らの医療を支えているのです。 本書は、彼ら非医療部門のスタッフをクローズアップしているところに特徴があります。 そう、お医者さんや看護師さんでなくても、MSFのスタッフになることができるのです。ただし、スタッフになるには、実務経験と語学力(英語またはフランス語)が重視されます。 となると、採用されるのは簡単なことではありません。ですが、MSFの採用審査は、落とすためのものではないとのこと。この方面で実務を積んではどうか、この分野を強化するとよい、といったアドバイスをもらい、何度目かの挑戦で採用される方も多いそうです。本書では、そのようなスタッフの話も紹介されています。 専門性と活動理念とによって高く評価されるNGOやNPOは、その活動に共鳴する人々にとって理想の職場であり、憧れの的となっています。MSFでは、定年後あるいは子育てが終わってから活動する人も多いそうですよ! 「国境なき医師団」になろう!
いとうせいこう(著) 講談社現代新書(2019年) 「国境なき医師団」で働くのは医師や看護師だけではない!現地ルポと日本人スタッフへのインタビューで迫る、「人道主義」の最前線 出典:amazon  橋本 信子
同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











