フィンランド公共図書館 躍進の秘密(吉田右子 他)
 |
|
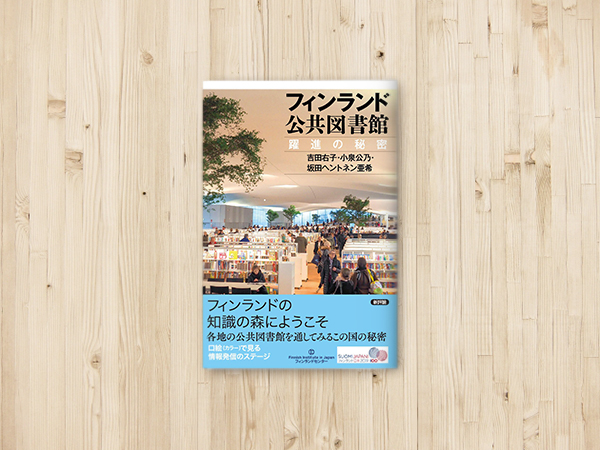 図書館は「住民の居間」 フィンランド公共図書館
躍進の秘密 吉田 右子 (著), 小泉 公乃 (著), 坂田 ヘントネン亜希 (著) 「学力世界一」と評判の高い北欧の国フィンランドは、図書館大国でもあります。国民一人当たりの貸し出し冊数や図書館予算は世界的にもずばぬけて高く、国民の約7,600人に一館の図書館があるとのこと。日本は約3万8,000人に一館です。
フィンランドでは、図書館は「住民の居間」と呼ばれ、「勢いよく」使う人びとでにぎわっているといいます。なんだか楽しそうですね。 子どもから大人までの幅広い年齢層の人たちが図書館を活用しています。 学校と公共図書館とが密に連携し、子どもたちは授業の一環として日常的に図書館を訪れているそうです。 生涯学習の場としても活発に使われています。さまざまな講座や、編み物のつどい、アートの展示、コンサートなどにも利用されています。図書館で仕事をする人もいます。 おしゃべりも、飲食も、節度を保てばOKです。まさに、みんなの居間ですね。静寂を必要とする人のためには、そのための読書室を設けるなどして配慮しています。 図書館が所蔵しているのは、本や新聞、雑誌、視聴覚資料(CDやDVDなど)だけではありません。コンピュータゲームを楽しむこともできるそうです。 ものづくり工房も設けられていて、工具や3Dプリンタ、ハイスペックなIT機器、ミシンなどが使えます。音楽練習室やスタジオを備えているところ、スポーツ用品やレジャー用品を貸し出しているところもあります。 そのように「進化」した背景には、図書館が、本を読むことを中心とする伝統的なリテラシー(情報の収集、取捨選択、読解、活用能力)だけではなく、言語、視覚、聴覚、運動感覚などマルチリテラシーを身につけるための場へと転換がはかられているということがあります。 図書館にコンピュータゲームがあるのも、そのためです。ゲームもメディア文化のひとつであり、家庭で購入できない子どもにもアクセスする機会を提供するべきだという考えです。 そしてなにより、図書館がフィンランド社会の目標である平等の達成を支える役割を担っている、という意識が浸透していることが大きいでしょう。図書館は、移民などのように外国に背景をもつ人びとも含めて、あらゆる人が情報や文化にアクセスできることを追求しているのです。 そのため、行政のワンストップサービスが受けられるよう、生活相談や育児支援、若者支援のコーナーが設けられていて、専門家が常駐する図書館もあります。 面白いのは「フローティングコレクション」のシステムです。複数の図書館ネットワークが共同で本を所蔵しているとみなして、返却された本はそのまま返却された館に置かれます。他館で請求があれば、本はその館に送られます。こうすれば、借り出された本をいちいち返却する郵送費や人件費が減らせるというわけです。 またスタッフも、所属館を固定せず、機能ごとのワーキングチームを結成する「フローティングオーガニゼーション」という形をとっています。本も人も、縦割りで所属するのではなく、横断的に流動させるという考えかたは、どこにでも適用できるものではないでしょうが、図書館に限らず組織運営のヒントになりそうです。 同じ出版社から、世界の図書館界をリードする北欧やオランダの図書館事情を紹介する本も出ています。アメリカの図書館事情については、少し前の本ではありますが、菅谷明子『未来をつくる図書館 ニューヨークからの報告』(岩波新書 2003年)がたいへん面白いです。 フィンランド公共図書館
躍進の秘密 吉田 右子 (著), 小泉 公乃 (著), 坂田 ヘントネン亜希 (著) 新評論 フィンランドの知識の森にようこそ。各地の公共図書館を通してみるこの国の秘密。 出典:amazon  橋本 信子
同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











