仲間と読み深める読書会のすすめ(深川賢郎)
 |
|
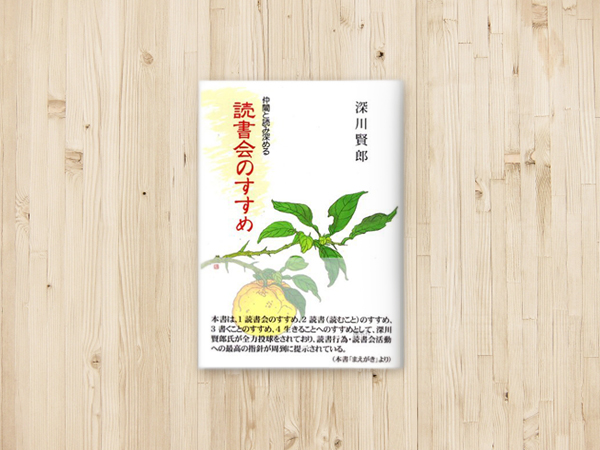 「自己を解放」し「自己を回復」する読書会 仲間と読み深める 読書会のすすめ
深川賢郎(著) 今回ご紹介するのは、広島県で10年以上続いてきた読書会について綴られた本です。著者の深川賢郎さんは、高校の国語の先生でした。定年退職後も生涯学習としての読書活動に力を入れておられます。
深川さんが講師を務めている読書会は、もとは町の読書活動活性化のために公立図書館が企画した会でしたが、その後も自主的な会として継続しているものだそうです。 確認したところ現在も続いているようですので、なんと20年以上継続していることになりますね。すごいことです。 読書会は月一回開かれますが、メンバーが輪番制で世話役となり、課題図書の選定と当日の司会進行とを担当されます。課題図書は県立図書館の集団読書用のリストから選ぶことが多いそうです。 読書会継続の秘訣は、参加者が対等であること、みんなに発言、発表の機会があること、正解を押し付けたりしないことのようです。 読書会は、本を読むのはもちろんですが、「人の話を聞く会」「自分の思いを述べる会」でもあります。そのため、のびのび発言できる雰囲気が必要です。 そこで、深川さんは、まず本を自由に読むこと、そして自由に発言することを重視されてこられました。多少思い込みが強い発言が出たり、読みとりが今一つであったりしても、指摘や修正は控えておられたそうです。回を重ねるうちにそうしたところは修正されるのだそうです。とても含蓄のある言葉だと思います。 そうして毎月読書会を重ねるにつれて、参加者の読書の仕方に個性が出てきたといいます。課題図書の作家の作品を数編読む人、同じ題材で異なる作家の作品を読む人、舞台となった土地の地理や風土を調べてくる人、登場人物のせりふから作者の問題意識を読みとる人など、それぞれの「読み」が、深みや広がりを持つようになったそうなのです。 読書はそれ自体、個人作業です。でも作品をめぐって自分の考えを人に伝えたり、議論したりすることを通して「自己を解放」し、「自己を回復」することができると深川さんは言います。 さらには、そのような時間をともにする仲間との間に豊かな人間関係が築かれているそうです。作家ゆかりの土地で読書会を開いたこともあったそうですよ。素敵ですね。 なお、後半は深川さんの読書ノート(書評)から何作品かを掲載されています。取り上げている作品以外の文献も参照し、作品の主題を深く、かつ発展的に読みとられています。文章が綺麗で、流れや勢いがあるので一気に読めます。 仲間と読み深める 読書会のすすめ
深川賢郎(著) 渓水社 JPIC読書アドバイザーの読書会立ち上げから10年にわたる活動の記録と実践。「読むことは根を育て、書くことは実を育てる」の意識を基に、豊かで充実した読書を追及する。 出典:amazon  橋本 信子
同志社大学嘱託講師/関西大学非常勤講師 同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得退学。同志社大学嘱託講師、関西大学非常勤講師。政治学、ロシア東欧地域研究等を担当。2011~18年度は、大阪商業大学、流通科学大学において、初年次教育、アカデミック・ライティング、読書指導のプログラム開発に従事。共著に『アカデミック・ライティングの基礎』(晃洋書房 2017年)。 BLOG:http://chekosan.exblog.jp/ Facebook:nobuko.hashimoto.566 ⇒関西ウーマンインタビュー(アカデミック編)記事はこちら |











