<ふつう>から遠くはなれて(中島義道)
 |
|
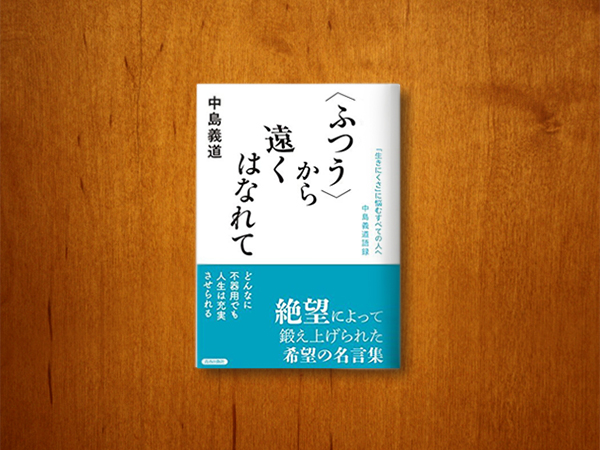 「なぜ生きるのか?それを知るために生きるのだ」 <ふつう>から遠くはなれて
中島義道(著) 先日、カーラジオを聞いていたら、中島義道さんという哲学者のコラムが紹介されていました。
今、話題の時事問題を「ウソ」という切り口で言及したもので、“嘘はついてはいけません”と大真面目に教育しているにもかかわらず、世の中には「知らぬ存ぜぬ」が横行している…。 しかし、生きるために必要なのであれば、この際「ウソはつかない」という美徳を外してはどうか、といった内容でした。 ちょっと面白いなと思い、早速手にした一冊です。 (本文よりp.3-4) 小学生のころから、自分が自分の意思ではなく生まれてきて、あっという間に死ぬというこの残酷な事実を「解決する」ことが生きる目的だと思っていた。… そして、三〇代の後半にやっと哲学でメシが食えるめどが立って、私は「死」を直視していい環境が与えられるとともに、哲学の研究がアホらしくなっていった。 というより、どんなに本を読んでも、どんなに勉強しても「死ななくなる」ことはないであろうと思われ、哲学とは所詮むなしい「気晴らし」にすぎないのかもしれない、という想念が身体の深いところから突き上げるように噴出してくるのを感じました。 小学生で「死」を意識するとは、驚きです。
ですが、以前知人がこんなことを言ってたのを思い出しました。 「私は小学生の時に、13歳の姉が亡くなって、それからは自分の人生は付録だなって思ったんです」 その方は、付録の人生だから楽観的に生きるようになったと、笑っておられました。 毎日、確実に「死」に向かって歩みを進めているのですが、もちろん普段はそんなこと考えないわけです。 それに、死が残酷なのか、その反対なのかも分かりません。 (本文よりp.88) 自分の「願望」に忠実になる 「なぜ生きるのか?」という問いに対して、「それを知るために生きるのだ」という回答が、いちばんすぐれているようにぼくは思う。 「きみはなぜ書くのか?」それを知るために書くのだ。 (本文よりp.113) すべて自分が選びとったものだと考える 他人によって押しつけられたものが苦痛を与えるとき、われわれは脆(もろ)く崩れてしまう。だが、自分が選びとったものがたとえ自分に苦痛を与えるとしても、耐えられるのである。 自分が選びとった大学、自分が選びとった結婚、自分が選びとった職業は肯定するほかないではないか。 頭でぼんやりと浮かんでいたことが、はっきりしました。
筆者が死を真正面から見つめるからこその言葉です。 私が音楽を職業にしようと思ったきっかけは、意外にもモーツァルトのオペラ作品でした。 「コシ・ファン・トゥッテ」という喜劇です。 物語は、姉妹それぞれの恋人が彼女たちの貞操を試す…と言った、実に退廃的なテキストですが、音楽の美しさはさすがモーツァルトです。 大学4年の秋に、授業の一環で参加したプログラムで、“オケピット”という、舞台の下に作られた空間で演奏するのは普段にないワクワク感がありました。 舞台上の歌手とオーケストラが、一体になって創り上げる総合芸術は体験したことのないスケールで、皆の呼吸を合わせながら形になるプロセスは、唯一無二の楽しさでした。 今思えば、音楽の素晴しさを身体で感じ取ったんだと思います。 こうして書きながら、音楽を選んだ時の熱い気持ちや原点を思い起こすと、長く険しい音楽の道を貫く勇気が湧いてきました。 <ふつう>から遠くはなれて
中島義道(著) 青春出版社 不器用に生きる人への「生き方」指南の書『カイン 自分の「弱さ」に悩むきみへ』、 仕事としっくりいかず、生きがいを見いだせない人に向けた『働くことがイヤな人のための本』、 日常的にふりかかる「嫌い」の現実と対処法を説いた『ひとを〈嫌う〉ということ』など、 仕事、孤独、人間関係、対話、日本社会論…と、多岐にわたるテーマに思索をめぐらし、 これまで65冊の本を書いてきた著者の主要著書20冊より人生に役立つ名文章をまとめた著者初の名文集。 出典:amazon   植木 美帆
チェリスト 兵庫県出身。チェリスト。大阪音楽大学音楽学部卒業。同大学教育助手を経てドイツ、ミュンヘンに留学。帰国後は演奏活動と共に、大阪音楽大学音楽院の講師として後進の指導にあたっている。「クラシックをより身近に!」との思いより、自らの言葉で語りかけるコンサートは多くの反響を呼んでいる。 HP:http://www.mihoueki.com BLOG:http://ameblo.jp/uekimiho/ ⇒PROページ ⇒関西ウーマンインタビュー記事 |











