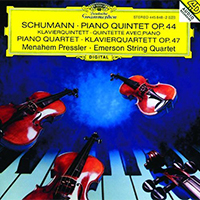アランの「幸福論」(アラン/ 笹根由恵)
 |
|
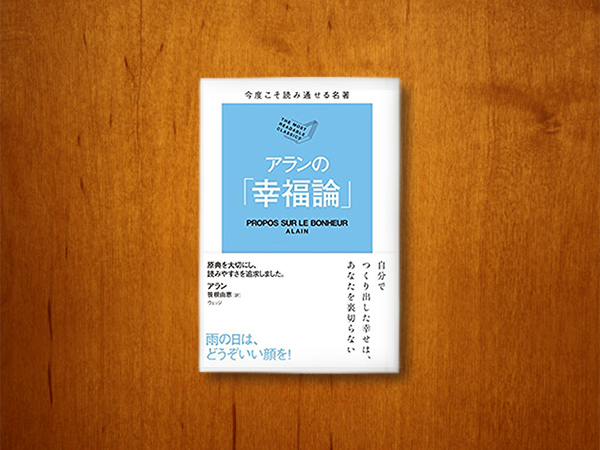 幸福とは何か?どうしたら幸せになれるのか。 アランの「幸福論」
アラン(著) 「幸福論」は、以前からずっと興味があったのですが、何となく後回しになっていました。
そんな中、新しい訳書が出版されたのを知り、運命を感じて手にしました。 アランは100年ほど前に生きた、フランスの哲学者です。 幸福とは何か?どうしたら幸せになれるのか。 普遍的な問題に分かりやすく迫った一冊です。 (本文より) 遠くを見る――目の緊張がほぐれると、思考は羽ばたき、健康になる 憂うつになっている人にわたしが言えることは、たった一つ。「遠くを見ましょう」ということです。~ どんなものも、そのなかに存在理由があるわけではありません。だから、わたしたちは自分自身から遠ざかってみるのがいいのです。それは、目にとっても心にとっても健全です。そうすることで、思考はその故郷である宇宙で羽を伸ばし、あらゆるものと結びついている体の働きと調和するでしょう。 あるキリスト教徒は「天はわが祖国なり」と言いましたが、これほど確信をついた言葉だったとは、言った本人も思っていなかったことでしょう。 遠くを見ましょう。 1911年5月15日 イタリアの音楽祭に行ったとき、敬愛する恩師に教えてもらった景色を思い出しました。
真っ白ならせん階段を上った先には、エメラルドグリーンのアドリア海がキラキラと美しく広がり、それを眺めていると、心が洗われるようでした。 そして、“自分”という小さな枠を外して、もっと自由に演奏できたらと思ったのです。 何より、先生が、 「あの景色を見ていたら、自分の悩みなんてちっぽけに感じるわ」 とおっしゃったのが印象的で、憧れの先生がそんな気持ちになることに驚いたのを覚えています。 「幸福論」を読みながら、なぜイタリアの夏を思い出したのか? そこには、幸せな音楽がつながっていました。シューマンのピアノ四重奏曲作品47です。 この曲の3楽章は、チェロの優しさあふれるソロから始まります。 チェリストなら、誰もが弾きたいと魅了されるメロディーでしょう。 実は、これが勉強したくてイタリアへ行ったのです。 シューマン(1810-1856)についてお話ししましょう。 彼はピアニストになりたかったのですが、特殊な練習をし過ぎて指が動かなくなり、その後は作曲家として身を立てました。 師事した先生の娘と恋に落ちたものの、結婚を認めてもらえず、泥沼の裁判を経て、ようやく結ばれます。 この曲は、困難を乗り越えた結婚後に書かれたもので、彼の人生で、最も幸福な時代の曲なのです。 シューマンとアランがつながるとは、思ってもみませんでしたが、幸せに対して抱く気持ちは、どの時代でも共通するのかもしれません。 「幸福論」を読んでいると、幸せは身近にあり、もし、それが遠く感じるのなら、自分が遠ざけているのではないかと思いました。 アランの「幸福論」
アラン(著) / 笹根由恵(訳) ウェッジ 悪い運命はない。自分の仕事をきちんとしよう。幸せだから笑うのではない。笑うから幸せなのだ。今のことだけ考えよう。苦しみはやがて和らいでいく。自分の気分に無関心になること。自分を愛する人のために、自分が幸せになる。―幸せに生きるための知恵。原典を大切にし、読みやすさを追求しました。 出典:amazon   植木 美帆
チェリスト 兵庫県出身。チェリスト。大阪音楽大学音楽学部卒業。同大学教育助手を経てドイツ、ミュンヘンに留学。帰国後は演奏活動と共に、大阪音楽大学音楽院の講師として後進の指導にあたっている。「クラシックをより身近に!」との思いより、自らの言葉で語りかけるコンサートは多くの反響を呼んでいる。 HP:http://www.mihoueki.com BLOG:http://ameblo.jp/uekimiho/ ⇒PROページ ⇒関西ウーマンインタビュー記事 |